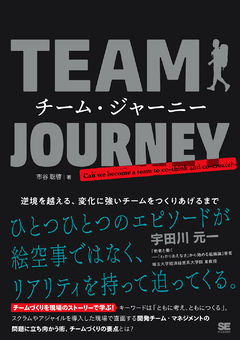新しいリーダーを迎えるチーム
僕はまた、会社を変えることにした。
これで3回、会社を辞めたことになる。今度の会社で4回目の入社。1社目は受託開発の会社で、3年以上勤めたけど、2社目と3社目は1年ほどしか在籍しなかった。決して後ろ向きな退職ではない。むしろ、1社目では素晴らしいチームメンバーに恵まれて、スクラムにも取り組んだ。僕は、1社目でチームで開発することに自信を持った。だけど、この自信が井の中の蛙かわずの可能性だってある。
だからこそ、安全な場所(コンフォートゾーン)にいつまでもいるわけにはいかないと考え、新天地を求めて会社を出たのだ。自分のチーム開発についての実践知が、他のレベルの高い環境でどこまで通用するのか確かめてみたかった。より自分を高めるための前向きな転職だった。
ところが……。2社目も、3社目も、外から見たり、聞いたりする分には先進的な会社だったのだけども。実際には現場がむちゃな開発スケジュールで疲弊気味だったり、部署や職種の間でマウントポジションをただ取り合っていたりと、とてもじゃないけどチームでプロダクトをつくっていくのに、理想的な環境とはいえなかった。皮肉なことに最初にいた会社の現場のほうが申し分のないチームになっていた。僕のチームのイメージは一人ひとりがきちんと約束を守り、お互いに貢献し合う関係性にある。
実際にこうして外に出てみると、どこもまともにチーム開発ができているとは言いにくかった。それはある意味で自分の自信にもなるのだけど、こんな風に組織の間をさすらいたいわけでもない。僕を送り出してくれたかつてのメンバーのことをよく思い出すようになった。
みんな、僕の思いに気がついていて「ここよりもっと高いレベルの開発ができる場所がある。太秦はもっと活躍する開発者だ」と面と向かって励まし、送り出してくれた。正直、一つ目の会社に戻ろうかと心弱くなることも増えてきたが、みんなとの別れを思い出しては踏みとどまっていた。
4社目は、デベロッパー向けのツールを開発、提供している、小さなベンチャーだった。会社の名前はアップストン。まだ、創業して5年程度だ。おそらく、全社員で30名もいないくらいの規模。もともとの成り立ちは、中堅SIerの子会社らしいのだけど、独立してからはあまり関係性があるわけではないらしい。SIの文脈と自社プロダクトの文脈は決して相性が良いわけではない。僕はできる限り制約なくプロダクトづくりに飛び込んでいきたいので、親会社からの縛りがないのは好都合だ。
最初はソフトウェアテストを支援する地味なプロダクトをつくって提供していたらしいが、今は複数のプロダクト開発に取り組んでいると聞く。どれも開発を支援するツールで、開発現場の環境(開発者の体験/デベロッパーエクスペリエンス)をより良くするというミッションを掲げている。このミッションも、この会社に惹かれた理由の一つでもある。デベロッパーエクスペリエンスをより良くしよう!と言っている会社がまさか自社内をひどい状況にしているとは考えにくい。
僕が配属されたのは、タスク管理をメイン機能としたツールの開発チームだった。ちなみに、中途採用ながら同期入社が2人もいて、それぞれ別々のツール開発チームの配属となった。
「なんで太秦が、タスク管理ツールなんだろうな。」
配属結果の連絡を一緒に聞いて、明らかに不満げな様子を見せたのは同期入社の一人の御室だった。僕とは同じ年齢らしい。
「この会社にとって、タスク管理ツールはテスト管理ツールに続いて社長の期待が大きいプロダクトらしい。」
この会社はプロダクトのコードネームに番号を振っていて、会社の成り立ちともいえるテスト管理ツールはゼロと呼ばれている(確かユーザー向けには「テストアップ」という安直な名前がつけられて提供されているはずだ)。僕が入るタスク管理ツールは、フォースと名付けられているそうだ。アップストン社には、他に世に出ているプロダクトは今はなかったはずだから、フォースより前にあったであろう3つのプロダクトは残念な結果に終わっているのだろう。だから、フォースにはゼロに次ぐ期待がかけられているというのは御室の言うとおりかもしれない。
それなのに、なんで俺ではなくて、お前なんだと。御室はにらみつけるようにこちらを見る。御室の開発者としてのこれまでの実績は明らかで、僕よりはるかに即戦力で動けるだろう。御室は自分自身について相当な自負心を持っているようだ。御室に責められて僕の胸が早鐘を打ち続けていると、もう一人の同期入社が間に入ってきてくれた。やはり僕と同い年で、眼鏡の奥に細い目を忍ばせた宇多野だった。
「タスク管理ツールは、今チームが混乱していて大変だと聞きました。チーム開発でスクラムの経験がある太秦さんが、私たちの中で最も適していると思われたのでしょう。」
宇多野の口調は、静かでそれだけに説得力が高く聞こえた。御室も言い返せないようで、その後は僕のほうを見ることはなかった。宇多野は気にすることはないとばかりに細い目をへの字に折り曲げてみせた。
来週からチームリーダー、やってくれる?
「太秦さん、来週からこのチームのリーダーを頼むよ。」
僕は自分の耳を疑った。そして、相手が本当にそう言ったのか確かめるように目の前の男性を見上げる。やけにガタイが良い、プロダクトオーナーの砂子さんだ。
「……今なんて、言われました? 私がこのチームに来てからまだ1か月も経っていませんけど……。」
「知ってる。今日で、11営業日だ。」
「いや、あの、まだチームリーダーに会って話もしていません。」
「そうだな。でも、もう二度と会えないかなー。辞めちゃったから。」
冷たさを感じる嫌な汗が顔をつたい始めた。状況の深刻さに反して、砂子さんの余裕の吹かせ加減が異様に感じられる。
(僕が、このチームのリーダーをつとめるだって……!?)
不意に背後に気配を感じた。いつの間にか僕の後ろにチームのメンバーが並んでいる。
「……なんだまた辞めたのか。」
ひときわ大きな体で、貫禄のあるメンバーが口火を切った。このチームの最古参、嵐山さんだ。もともとタスク管理ツール「フォース」の原型をつくったのが嵐山さんで、誰よりもプロダクトのことについて詳しい。そして、誰よりも態度が横柄だ。チームメンバーからはひそかに“皇帝”と呼ばれているが、そんな高貴さなんてまったくない、ただのジャイアンだ。
「まあ、しょうがないっすよね。ついていけない人にはバスから降りてもらうしかないですよね。」
これまた、さらっと怖いことを口にするのが皇帝と同じく初期の頃からチームにいる天神川さんだ。年齢も皇帝に次ぎ、早口で自分の見解をまくしたてるため、チームの若いメンバーはたいてい押し込まれている。
「お二人とも言いすぎですよ。太秦さんのドキドキがこちらにも伝わってきます。」
皇帝と天神川さんの横に並ぶと、細身で小柄な体がさらに小さく見える、三条さんが眼鏡を押し上げながら、早口でたしなめた。三条さんまで早口なのは、皇帝、天神川の2人にはっきりと聞こえないようにするためだろう。彼らに意見をしたら、即座に反撃を受けてしまう。さすがに、このチームの経験がそこそこある三条さんは上手いものだった。だが、もちろん2人の耳には届いていないので何の効果もない。
「………。」
三条さんの横に立つのは、鹿王院くん。僕よりも若く、三条さんよりさらに細身に見える。不用意な発言をすることはないが、それは皇帝と天神川さんを恐れているというよりは、やりとりが面倒なので何も言わないようにしている、という感じだった。三条さんと同じく眼鏡をしているため、皇帝に時々“眼鏡兄弟”と冷やかされている。
「……これで、2人目ですね。」
端っこに立っていた女性が静かに言い放った。このチームでは最年少にあたる有栖さんだ。有栖さんも物静かで、ほとんど自分の意見を言うことはない。
「いや、もう4人目だ。」
皇帝が即座に訂正する。有栖さんがこのチームに加わる前にすでに2人がリーダーを降りていたということだろう。僕は思わず、つばを呑み込んだ。やれやれという感じで、砂子さんがため息まじりに言った。
「このチームのプロダクトもローンチしてからもう1年、初期のMVP開発の頃からするともう2年近くも経過する。そのわりにはまだまだ鳴かず飛ばずだ。」
そんなプロダクトのPOを引き受けて、俺はつらいんだとばかりに、砂子さんは恨めしそうに僕らチームをながめた。僕は自分が少し落ち着いてきたのを感じて、砂子さんに反撃を試みた。
「そんな大事な時期を迎えるプロダクトのリーダーなんて、僕にはとてもつとまりません。」
チーム開発を経験してきたとはいえ、僕はまだチームリーダーなんてやったことがないのだ。急に来週からリーダーだと言われても、一体何から始めたら良いのか。
「それはないでしょう、太秦くん。会社は君ならリーダーをやれると踏んで、採用したんだから。」
砂子さんが答えるより早く皇帝が不必要に大きな声で呼びかけてきた。天神川さんもそれに同調する。
「それに、このチームはだいたいこのメンバーでもう何か月もやってますからね。チームプレーは良いと思いますよ。」
なぜだろう、天神川さんの後押しの言葉にまったく真実味が感じられない。この2人以外、三条さんも、鹿王院くんも、有栖さんも、みんないきいきとチーム開発をしている感じはない。あまり意見を出さないので、3人いても存在感が薄い。前任者のリーダーも現場に来られなくなってしまうなど、このチームが問題を抱えているのは明らかだ。僕の頭の中で嫌なイメージが先走り、大きくなっていく。
(ここも1年くらいで終わりだろうか……)
僕が気を遠のかせていると、不意に視界の端で見慣れない人がみんなと同じように立っているのに気がついた。砂子さんも、そういえばそうだったとばかりに、急にその人のことを紹介し始めた。
「太秦さんもいきなりこのチームのリーダーをふられていろいろと不安だと思うので、助っ人としてこのチームのコーチを用意した。」
砂子さんに促されて前に出てきたのは、鹿王院くんや三条さんに近い細身で、どちらかというと冷たい雰囲気をまとわせた人だった。
「蔵屋敷です。」
彼のぶっきらぼうなことこの上ない自己紹介が、僕の心に留まることはもちろんなかった。
僕は何もわかっていない
突如ふって湧いたリーダーへの着任。僕のリーダーとしての1週目は気がついてみたらあっという間に終わっていた。あっという間に終わって、残ったのは不安しかない。一向に慣れないチームメンバー、まだよくわかっていないプロダクト、僕自身のリーダー経験の薄さ、そして、チームにあまり絡まないが開発機能だけはきっちりノルマのように積み上げるプロダクトオーナー。
ただ、今挙げたこと以上に僕の心を落ち着かなくさせる存在がある。もちろん、皇帝だ。何かにつけて皇帝からの圧を感じて胸苦しくなる。まるで「俺が言ったことは、そうなって当然だ。できないなんて言葉は存在しない」という前提が置かれているようだ。この皇帝のどうにもならなさ加減と、プロダクトオーナーの問答無用の要請の間で板挟みになることが目に見えていた。リーダーが4人も入れ代わり立ち代わりするわけだ。
他のメンバーも皇帝の圧は感じているようだが、とにかく事を荒立てないように発言を控えている。静まり返った集団が、黙々と言われた仕事をこなす現場。このチームの異様さはこれまで僕が経験したことのないものだった。
週の最後の営業日を迎え、チームのみんなはさっさと帰ってしまったが、僕はなんとなく自席に残ってしまう。やることが積まれているわけでもない。なんともいえない不安が見えない力となって僕を椅子に押しつけているようだった。フロアにほとんど人がいなくなっても立ち上がれない僕に、近づいてきた人影があった。蔵屋敷さんだった。コーチという、開発現場ではあまり耳慣れない役割に、皇帝を始めチーム一同が彼をどう扱えば良いのかわからないままでいた。
助っ人だと砂子さんは言っていたが、彼とはこの1週間一度も口をきかなかった。何がコーチだ。僕は不安を怒りに変え、彼が何かを言うよりも早く自分の気持ちをあふれさせていた。とにかく誰かにこの状況の文句を言いたかったのだと思う。
「僕には無理ですよ。チームはひとくせもふたくせもある人たちばかり。そもそもプロダクトだって上手くいってないし。何よりも僕は、リーダーなんてやったことがないんですもの……!」
そこまで吐露しているというのに、蔵屋敷さんはいまだ一言も言葉を発しない。ただじっと僕をながめている。この人は一体何者なのだろう?と畏れにも似た感情を湧かせ始めたところで、ようやく蔵屋敷さんは口を開いた。
「君が知っていることは何だ?」
「……え?」
今なんて言った? 僕が知っていること? 僕は蔵屋敷さんの言葉を待ったが、彼は冷たい視線を僕に送り続けるだけだった。この間、蔵屋敷さんの問いが僕の中を駆けめぐる」
何を知っているのか? このチームの? このプロダクトの? いずれにしても、僕はまだ何も知らないと言っていいということに気がついた。
何も知らないのに、自分の偏った想像力だけを働かせて、この先の展開をイメージし、そのイメージに縛られている。僕の考えがそこまでたどり着いたとき、蔵屋敷さんは静かに、そして唐突に言ってのけた。
「君は、まだチームとは何かを知らない。」