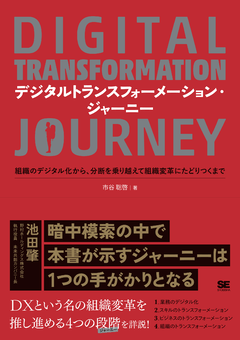本記事は『デジタルトランスフォーメーション・ジャーニー 組織のデジタル化から、分断を乗り越えて組織変革にたどりつくまで』の「第1章 DX1周目の終わりに」を抜粋したものです。掲載にあたって一部を編集しています。
この国にとってのDXの意味
「DXとは、本当のところ何を意味するのか?」 実に難しい問いです。DX(デジタルトランスフォーメーション)という言葉に込める意図は企業、人によって様々です。この問いに向き合う立場によって違ってきます。日常業務におけるデジタルツール、技術の活用によって効率化を進めることであったり、新たなビジネスモデルを構想し事業を生み出していく場合もあります。そうした取り組みが同時に行われることも、あるいは移り変わっていくこともあります。
捉え方によって目指すところは異なり、取り組みようも変わっていくことになる―ですから「本当のところ」と問いに加えています。私たちは“DX”を通じてどこへ向かいたいのか、その回答自体が取り組む過程において変わっていく可能性があるということです。
それはさながら、おぼろげに捉えている方角に踏み出し、少しずつ見えてくる情景を手がかりに自分たち自身がどこへ向かうべきなのかを探り巡る旅(ジャーニー)のようです。DXとは何を意味するのか、そしてどのようにその旅を始め、続けていけばよいのか。ここに、本書を通じて向き合っていくことになります。DXという言葉が持つ意味を探っていくために、まずその背景から捉えていきましょう。
2020年の地球規模の感染症拡大によって日本ではデジタル化の進展について民間企業はもちろん、行政の領域においてもその機運を大いに高めることになりました。業務のオンライン化やリモートワークへの急遽の対応に端を発して、その後も給付金申請をはじめとした行政手続き、学校や医療のオンライン対応など実に様々な混乱を露呈する形となりました。これらの事象が連日報道を賑わせ、日本のデジタル化の立ち遅れをはっきりと示すことになってしまったわけです。
「いかに非接触のまま人と人とが目的の所作を果たすか」ということは容易に解決しきれない、継続的に取り組むべきテーマとなっています。こうした状況が「デジタル化を促す」「これまでの業務や行動のあり方を見直す」という機運に繋がり、結果的にDXへの取り組みを後押しすることになったのは事実です。
2020年夏には経済産業省から国内のDXに取り組む企業を評価し、その先進事例を紹介するDX銘柄の最初の発表がありました。この発信にはDXに取り組む企業への国としての期待を明らかにするとともに、他の企業にとっての手本となる事例の提供がその狙いにあると考えられます。国としてDXの推進を後押ししていく流れと、民間企業のDXへの関心の高まりが一致し、はからずもDX元年とも言うべき年になりました。
こうした動きを皆さんはどのように感じているでしょうか。「DXなんてただのバズワード」「デジタル化の名の下に手段が目的になっている」といったネガティブな印象を持たれている方もいるでしょう。事実、手段の目的化が起きているところも少なくありません。私もDXという言葉が持つ本当の価値に気づいたのは、大企業から中小企業に至るまで幅広く組織支援、事業開発に関わる中でのことでした。
DXとは単にこれまでの業務をデジタル化するという話でも、何らかのツールを導入するだけという話でもなく、この言葉によって「これからの組織のあり方を変える」という風向きを生み出せる絶好の機会なのです。DXへの期待とは、組織変革への機会と言いかえることができます。なぜ、そう言えるのか? 1つずつ読み解いていきましょう。まず、この国が置かれている、今ここの「現在地点」とはどのようなものか、から。
日本のDX、その出発地点
その題材としては、経済産業省が提示している「DXレポート」が俯瞰するには格好の内容と言えます。DXレポート(2018年版)は、「2025年の崖」という言葉を広めることになった有名な文書です。「2025年の崖」とは、既存のITシステムの保全が行き届かず、業務停止など様々な問題を引き起こし、経済活動への多大な損失を与える事態を2025年以降迎えることになる、という予測を指します。
先に述べたようにDXとは、既存の業務のカイゼンにデジタルを活用しようという狭い目的ではなく、社会や顧客に新たな価値を提示するための挑戦的な探索です。既存の業務を従来どおり行えるよう、ITシステムの保全を目的とした「守りの投資」に対して、いまだ存在しない価値を創り出す狙いで「攻めの投資」と言われる領域です。ところが、こうした攻めの活動よりも、守りのための活動に資金も時間も多大に費やさなければならないという実態があります。現代の企業が抱える「IT資産のレガシー」問題です。この問題への対処を誤る、あるいは対処がなされないまま進むと、先の2025年には既存ITシステムの保全すらできなくなると言われているのです。
IT資産のレガシー問題は、その対処のための体制の維持とコストに関するだけではありません。攻めの投資としていかに新たなサービス提供に乗り出したところで、既存ITシステムが企業のデータ利活用を阻む要因となってしまう課題に直面します。DXに取り組む企業が競合他社やディスラプターに対してアドバンテージとなりうるのが、これまでの顧客との関係性や顧客と共有してきた経験そのものであり、具体的にはデータ資産に他なりません。ところが、顧客やサービス提供に向けて必要なデータを取り出そうにも、既存のITシステムがそうした用途に対応しておらず、適応させようにも相当なコストと期間を要してしまうという状況に立ち往生するということが少なくありません。
理由として既存システムを改変しようにも、「システム内部の構造に不明なところが多くその影響範囲の調査、特定に多大な時間を要してしまう」「従前より決まっている、既存の施策や取り組みに対応するのに手一杯で、新たな開発に対応できる体制が存在しない」など、レガシー環境に共通する問題が挙げられます。こうした事態もまた珍しいことではなく、多くの組織で必ずといってよいほど見聞きすることです。なぜ、ITシステムはレガシー化するのでしょうか。
それは、ただ採用している技術が陳腐化してしまうから、という理由だけではありません。たとえ、技術が一般的に古くなってしまったとしても、ITシステムに対する継続的なマネジメントが適用されていれば「透明性」は確保できます。内部構造の具体的な説明を残すだけではなく、「なぜ、そのようにしているのか?」という理由と目的を言語化し、あとから関与する者でもわかるようにしておくこと。こうした知識の保全が組織の課題として認識され、運用化できていればシステム自体の透明性を保つことはできます。
ところが、また厄介な問題が顔を見せることなります。単にシステムに関する知識を保全できていればよいわけではなく、その知識を活用する体制の保全が問題となるのです。長期間にわたる体制を維持するためには、「継承」に関する仕組み化が必要となります。この問題はITシステムに関してだけではなく、専門技術を必要とする領域では広く起きていることです。ハードウェアや産業用機器、設備の保守メンテナンスを担う技術者の高齢化によって、業界を問わず人手不足は増す一方です。この問題を抱える企業では「遠隔にいる熟練技術者と現場に臨む若手をデジタルに繋ぎ、リモートによる保守支援を行う」といったことがDXテーマの定番となっています。
こうした体制の保全は現場だけで対応しきれる課題ではありません。最初の運用体制が構築できれば「あとは現場におまかせ」では、人材の流動とともに徐々にすり減っていく体制を現場だけでは維持することができず、現場は日常化した消耗戦を強いられることになります。
ですから、人材流動性に伴う課題は、組織として取り組む必要があります。実にシステムが次の刷新のタイミングを迎えるよりもはるかに速く、技術者のほうが流動していってしまうのです。技術者は自身のキャリアを作っていく上で、獲得できる経験、技術について敏感であり、固定化されることを基本的に避けようとします。構築した直後から技術的な陳腐を始めていくシステム環境と、技術者の志向性は根本的には真逆です。
ですから、前提として置くのは「体制の固定化」ではなく、「人材は流動する」という事実であり、それを踏まえた事業計画を組み立てておく必要があるのです。たとえば、事業継続計画(BCP)とは、自然災害や大規模な感染症などに起因した事業継続を危ぶむリスクに対応するための備えですが、こうしたプランニングにシステムの「継承」も織り込む必要性を感じます。そのくらい、システムのレガシー問題は現代における致命的とも言える課題に昇華しています。
実際、2025年を迎えるまでもなく、基幹システムの運用保守を担う体制が時代とともに貧弱化し、もうあと1名2名の人が辞めてしまったら、立ち行かなくなってしまうというギリギリの状況を目にすることがあります。取り返しのつかない、危機の進行は明らかなのですが、経営サイドの感度が欠けている場合、最後のブレーキがどこからも踏まれることもなくあっさりと崩壊へと至りかねません。「ITはよくわからない」という言い訳で現状をそのままとし、事業継続ができないという事実を前にするまで放置するというのでは、あまりにも無策で悲劇的です。
一方、いにしえより現代に至るまで、事業継承が行われている事例が日本には存在します。20年に一度遷宮を行う伊勢神宮です。20年のタイムボックスで、そのたびに社殿を新しくし、御神体を遷していく式年遷宮。20年と定めているのも、昔の人の寿命の上でも2回は遷宮を経験することができるため、2度目においては遷宮の技術を継承することに重きを置くことができるという一説があるようです。また、移築を終えた直後から人材の確保と技術伝承に取り掛かり、20年周期を守り続けています。システム構築の周期も、10年継続モノ、20年継続モノと、徐々に式年遷宮に近づいてきているようです。
知識や技術の継承が重要であるという認識は今に始まったことではもちろんなく、かつてはナレッジマネジメントという概念が盛り上がった頃があります。ナレッジの収集と蓄積を促すために具体的なツールの導入などが企業で盛んに行われていたのは2000年代前半頃までのことと記憶しています。当時の管理システムはナレッジの収集、管理のすべてを人力で行う必要があり、現場運用していくには相応の負担がかかっていました。当然現場からの評判は悪く、その結果、十分にナレッジが集まることがなく消えていってしまったと推察しています。
どう考えても組織においてナレッジマネジメントが機能しなくてよいはずがありませんが、「ナレッジマネジメント」という言葉が現代に至って死語になっているとおり、その仕組みが存在せずとも特に問題とはならなかったのです。その背景には日本の雇用のあり方が影響しています。
かつて、日本は「終身雇用」が前提となっていました。つまり、人材流動性が極めて低く、転職する人のほうが珍しいという時代があったのです。そうした環境では、組織に人が張り付くわけですから、結果的に人を介して知識も組織に残り続けるわけです。もちろん、特定の人に知識が内在化したままですから暗黙知が多く、仕事も属人的です。しかし、人が組織を離れない限り、仕事と知識が属人化しても大きく困ることはないという次第です。
このように考えると「終身雇用」という概念はナレッジ戦略の一種とも捉えることができます。ですから、人材流動性の高まりによって、終身雇用の前提が崩れて久しい現代においては、別のナレッジ戦略が当然必要となるのです。2025年の崖問題がクローズアップされているとおり、このあたりの課題認識はまだ十分ではなく、組織知をどのようにしてマネージしていくか、その再定義が必要となっています。これまで以上に知識を組織に蓄積すること自体を評価の対象とし、「組織知」を戦略的にマネジメントしていく取り組みが求められています。
さて、ナレッジマネジメントへの取り組みを見直していく一方で、目の前にはすでにレガシー化したIT資産があり、この扱いをいち早く決めて具体的に手を打っていかなければならない現実があります。既存システムのお守りを従前どおりのあり方でそのまま維持すればするほど、状況には進展なく、技術者への求心力を失い続ける一方です。そうなれば、余計に守りを固めていく他ありません。
2025年までに予想されるIT人材の引退、既存システムのベンダーサポート終了によるリスクの高まりで、生じうる経済損失は最大12兆円です。既存ITシステムについて、再構築なのか、部分的に切り出していくのか、あるいは廃棄するのか、その方針を定め、手を打ち始めていなければならないというのが、DXレポートが提示された2018年の警句(対処方針)なのです(図1-2)。

この警句から2年が経過し、2020年末に再度示されたのがDXレポート2です。2025年の崖問題という十分揺さぶりのある予言があったにもかかわらず、その後のレポートでは調査対象の企業の実に9割以上がDXにまったく取り組めていないか、部門レベルで散発的な実施に留まっているという状況にあると示されたのです。
DXレポート1の内容は、ITシステムのレガシー問題に振り切ってしまったため、「DXとはシステムのレガシー対策である」という短絡的なミスリードを引き起こすことになるのではないかという懸念も感じさせるものでした。ところが実際には、2018年より必要性が訴えられてきたDXへの対応がほぼ進展していないという状況なのです。レガシー化の本質とは、ITシステムが負債化することだけではなく、従来の延長の考え方、方法を問い直すこともなく適用し続けること、つまり組織文化のレガシー化にあると言えるのではないでしょうか。
DXとは何なのか
ジャーニーの出発地点の確認はここまでにしましょう。これから取り組んでいくDXという活動についてより具体的に捉えていくことにします。まずは、あらためて「DXとは何なのか」という問いから始めましょう。「DX」という言葉、概念自体をあまり好意的に受け止めていない人々もいるはずです。この言葉の得体のしれなさは、IT界隈でよく登場する「バズワード」に十分当てはまるところであり、敬遠したくなる雰囲気たっぷりです。
ただ、ここまでのとおり、日本企業の危機的な状況を突破していくためには、組織としての考え方と指針にあたる「組織文化」を変えることに踏み込んでいく必要があります。そのためには経営から現場まで、組織レベルとしての思考と行動の方向性の一致が不可欠です。こうした一致を生み出すための、共通目標・旗印となりうるのがDXという「機会」であり、そのためにこの言葉を「利用する」というスタンスを持って臨みたいところです。
DXという言葉が意味するところは、実際のところ何なのでしょうか。その定義が実は存在しています。スウェーデンのエリック・ストルターマン教授が2004年に「ITの浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる」という概念で生み出したのが始まりとされています。この定義自体は、「ITが社会の利便性をより高めていく」と捉えることができ、現代においては至極当然の内容と言えます。定義はあるものの言葉の利用にあたり、様々な人がそれぞれの意味を持たせた結果多義的になってしまい、DXを得体のしれない言葉に仕立てているという背景があります。
経済産業省が示したDX推進ガイドライン(2018年)では、DXの定義を以下のように示しています。
企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。
この定義は一文で構成されており、読み解きが必要になっています。図解したものが図1-3です。

「環境の変化」については、2020年に実に明確な破壊的変化がありました。もちろん、新型コロナウイルスによってもたらされた「コロナ禍」のことです。この感染症によって、人は非対面、非接触を、唐突に強いられるようになり、大きな混乱を迎えました。否応無しに環境の変化に対応せざるをえない、その結果として業務のデジタル化、リモートワークの導入が進んだのは事実です。
組織を取り巻く環境の変化とは、こうした「人に甚大な負の影響を与える状況の変化」だけではありません。むしろ、こうした行動変容をきっかけとして、人々の考え方や価値観自体が大きく変わっていく可能性があり、その変化の方向性は予測のつかないところです。ですから、今後とも「想定できない変化」への適応が組織には求められることになるわけです。
すなわち、DXとは単に「今現在の新しい技術を使ってサービスやビジネスを作りましょう」という話ではなく、変化に適応できる組織を目指し、その内部のあり方の変革を目指すものなのです。変化に適応できる組織だからこそ、その時々の状況に適した提供価値を顧客や社会に届けることができます。このように組織の考え方と行動自体を変えていくことがDXの本来の定義に織り込まれているのです。
さらに、DXを段階的に捉える考え方があります。段階は、デジタイゼーション、デジタライゼーション、デジタルトランスフォーメーションの3つです(図1-4)。

第1段階のデジタイゼーションとは、紙文書をはじめとしたアナログ、物理的な媒体をデジタルに置き換えるものです。何らかのツール・製品を導入して、紙のやりとりをなくすことで、大きな効率化が期待できるところです。
さらに進んで、第2段階のデジタライゼーションは、個別業務、プロセスのデジタル化にあたります。人力で行っていた業務を自動化するなど、デジタライゼーションもまた劇的な効率化をもたらす可能性があります。ただし、第1段階も第2段階も、先に述べた「提供価値の変革」までは及ばず、企業内のカイゼンに留まる状況と言えます。この段階までを指して、「DXを実践している」と胸を張るのはまだ早いというわけです。
第3段階に至って、本丸である「顧客に向けた新たな価値創造のための事業、ビジネスモデル変革」にたどり着きます。顧客にとっての新たな価値とは、これまでにはなかった新たな体験です。それは人力では到底できなかった個々の顧客に向けたパーソナライズされたサービス提供かもしれませんし、顧客のあらゆる行動データを総合して顧客の潜在的なニーズを満たすためのリコメンドになるかもしれません。そうした顧客体験を創り出すために、その礎となる第1段階、第2段階をいち早く進めることが期待されます。
DX1周目の敗北
さて、ここまでの話で官と民のかみ合わせもよく、DXに向けて一丸となって突き進んでいく姿が想像できるかもしれません。ところが、現実に組織を渡り歩いて垣間見えてくる様子は、そうした理想像からは遠い光景です。私が数十社の企業との関与から得たのは「日本のDX1周目(最初の周回)はすでに負けている」という感覚でした。
実はDXレポート2が提示する「DXはまったく進んでいない」という説を疑ってしまうくらい、多くの企業で関心が高まっており、それぞれの取り組みが始まっていると前線では感じていました。DXに関する指針、それは厚みのある計画書からアイデアレベルの内容まで濃淡はあるものの、各企業にはDXの名の下で思い描いている「絵」があります。
しかし、同時に文字通り、DXの「絵」はあるものの「実行」に移せていない、実行に移したところプロジェクトが火を噴いてしまう、という散々な状況が目に入ってくるのです。イメージ、戦略としては実に格好がよくても、肝心の実行についてはどういう体制で、どのような作戦で、いつどうなれば進めていけるのかが見えてこない。まさに、寓話一休さんに出てくる「屏風のトラ」のようなDXです。こうした事態が起きてしまうのは、やはりDXというワードが持つ得体の知れなさが影響していると考えられます。
「DXに対応した戦略」を創り出すために外部の支援者に丸投げしたり、世の中に転がっている「事例」を表面的になぞって生み出された「絵」は、組織の当事者が実行の算段を描けるようなものではなく、ゆえに実行できずに足踏みをしている。あるいは、実行に踏み切ったとしてもやはり十分な備え(具体的な作戦や体制)がなく、またはそもそも達成したいことがあいまいで、プロジェクトが破綻するという事態を迎えてしまうわけです。
一方、「絵」すらも描けていない場合もあります。DXの戦略がないということは、組織変革に向けた具体的な算段、取り掛かりがないということです。もちろん、何も始まることはありません。そうした状況でも「DXなんてバズワードだから」「デジタルは手段だから、それに引っ張られたくない」と、せっかくの変革の機会をふいにしてしまっている発言を聞くこともあります。
DXという言葉に振り回されてはいけませんが、この章で示したとおり、組織変革の旗印、組織内の共通認識を作るために利用する「機会」として認識するべきです。経営側からの現場を考えない一方的な打ち出しでもなく、現場での現場よがりなだけの活動でもなく、「組織が変わらなければこの先がない」という認識を経営と現場で揃えられる絶好のチャンスなのです。
だからこそ、「絵」は自分たちで描く必要があるのです。組織の外から見られても大丈夫なように、クールで綺麗な「絵」である必要はありません。そんなことよりも自分たちで見出した「次に向かう方向性」にあった組織の判断と現場活動を積み重ねていく。この組織判断と現場活動の一致を創り出せるかどうかがDXの成否を左右する最大の要因と見ています。
「絵」を描くのも、その絵を現実にしていくのも、難しい仕事だからといって外部に丸投げするようなものではありません。組織の変革そのものなのですから難しいのは当然です。それゆえに、DXとは段階的に組織をトランスフォームしていくジャーニーとなるのです。一気に派手な成果が得られるわけではありません。むしろ、その過程は実験を繰り返し、数々の試みから着実に学びを重ねていくための旅です。
この旅は、誰にとっての旅なのでしょうか。DXは経営の課題であると言われることがあります。確かに経営不在のDXはありえないでしょう。ですが、現実の変化を創り出していくのは仕事の現場、組織の前線です。だからこそ、経営と現場の方向性の一致が前提で、前者が欠ければ組織全体の活動にはならず、後者が欠ければ屏風にトラを描くことしかできないのです。DXとは、どこか遠くの先進的な組織がやるもの、あるいは組織の上層部だけで考えるもの、現場に丸投げしていれば勝手に進むもの、いずれでもありません。
では、どのようにして組織の一致を育みながら進めていくのか。次の章から旅に向けた一歩を踏み出すことにしましょう。