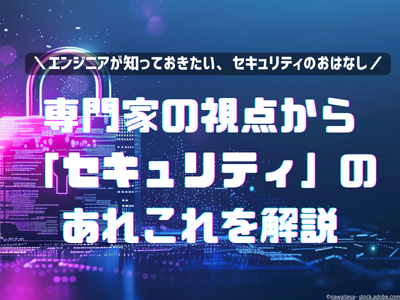重要なのは“ユーザー起点”でテクノロジーとつなげること
――コロナ禍の影響をうけ、いっそう加速しているDXのトレンドをどのように捉えていますか?
東樹 日本企業でDXが進みづらいのは、危機感の少なさがいちばんの理由なのではないかと感じています。
コロナ禍前は、実店舗をもつ企業にアプリ活用の提案をしても門前払いが多かったのですが、最近ようやく動き出したという印象です。日本の小売企業からは、国内の事例を教えてほしいと相談をいただくことがありますが、世界の事例に目を向けることも大切だと感じています。
もうひとつ大切だと思うのは、DXを一過性のトレンドとして捉えないこと。自分たちが取り組んでいる事業、ひいては生活している社会そのものを自分たちの手で変えていくという当事者意識が、名前だけのDXではなく、正しく進めるための根本になるのではないでしょうか。

鬼石 いち生活者の感想としては、ロボットやAIなどのテクノロジーが出発点となって生まれたテクノロジーありきのサービスや機能が多いように感じています。
多くのユーザーサービスを作ってきた感覚から推測すると、そうした機能はあまり使ってもらえないことが多い。
重要なのは機能ではなく、ユーザーの価値をどのように上げることができるかです。「こういった便利な世界にするためには何が必要なのか」など、ユーザーを起点とした機能やテクノロジーが必要なのではないでしょうか。DXを進めなければいけないからとりあえず取り組むのではなく、本当にユーザーの生活が便利になるものを提供していきたいですね。
――では、ユーザー視点のサービスづくりをするためには、具体的にどのようなことが必要なのでしょうか。
鬼石 機能やテクノロジーとの接地面になるUI/UXのデザインを、機能ベースではなくユーザー視点で考えること。これがなによりも大切です。
僕らがサービスを提供してきて感じることは、ユーザーに期待してはいけないということ。企業側がイメージする理想の形で、ユーザーがサービスを利用してくれることはほとんどありません。だからこそ、いかに利用するハードルを下げ、モチベーションを高く保ってもらうかをさまざまな角度から考え、工夫を施すんです。
たとえば店舗で利用するアプリであれば、まずアプリを位置情報と連携させて、店舗に入ったら店舗モードに切り替えてもらう、といった利用方法を考えても、ユーザーがわざわざ位置情報をオンにしてくれることはまれ。オンにするべき理由が伝わっていないんですよね。買い物というジャーニーの中で、ユーザーがどこで何を求めているかを考え抜いて、ここぞというタイミングでメリットを伝え、それを欲したときにオンにしてもらう。そういった体験や伝えかたをデザインする必要があると思います。
ユーザーが想像と同じように動いてくれないことを前提に、ホスピタリティをもって誘導し、その先に素晴らしいテクノロジーがある――。そういった世界観でサービスを設計することが、生活にいちばん浸透しやすいのではないでしょうか。

僕自身、キャリアのほとんどをデジタルデザインの領域で過ごしてきましたが、DX Design室の設立により、今後はさらに外の世界に領域を広げることができるのではないかとワクワクしています。
サイバーエージェントならではの大きな規模で、新しい取り組みをビジネスとして成立させていくことは、長い目で見れば日本全体を活性化させていくことにもつながるはず。外資系のテック企業が台頭しているなかで、日本の未来をいっそう元気にするためのチャレンジをど真ん中で進めていきたいです。
――鬼石さん、東樹さん、ありがとうございました。