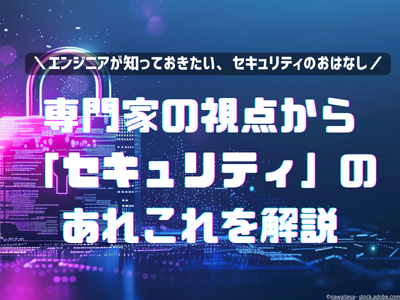The Linux Foundationは本日会見を行い、組織や今後の活動方針を説明した。Linux開発における情報交換や法的サポート、標準化について積極的な支援を行っていく。
The Linux Foundationは本日、東京ビッグサイトで開催されている「LinuxWorld Expo/Tokyo 2007」会場内で、組織説明や今後の活動計画に関する記者発表会を行った。同組織は、2007年2月にOpen Source Development Labs(OSDL)とFree Standards Group(FSG)が合併して設立された非営利のコンソーシアムで、Linuxの成長促進に取り組んでいる。

エグゼクティブディレクターのJim Zemlin氏は、Linuxのオープンソースによる開発効率の良さを多くの人に認知させ、利用してもらう第1段階は非常に成功を収めて終わったと述べた。The Linux Foundationは、今後予想されるLinuxベースとWindowsベースによるコンピューティングの二極化に備えて、Linuxの普及を促進するために設立されたと言う。
方策としては、マイクロソフトのソフトウェアプラットフォームが人類史上、一番成功したことを認め、「効率のよい宣伝活動」「プラットフォームの安心感」「グローバルな標準化」という3つの特長を、オープンソースのやり方で行うことを考えているという。また、メンバー企業とうまく協力し合いながら、プラットフォームの競合状態を乗り切っていきたいとも述べた。
具体的には、「プロモーション」「保護」「標準化」の3つの指針を挙げた。
Linuxの開発がシェアされるように、プロモーションもシェアする必要があるとし、The Linux Foundationでは中立な立場でその場所を提供する。例えば日本では年3回のシンポジウムが開催され、開発者同士の活発な意見が取り交わされる。
また、プラットフォームを保護し、安心して利用できる環境を整えることも重要であり、ライセンス問題など、開発に関する法的なサポートも行う。
Linuxの懸念事項の一つである、細分化によるハードウェア/ソフトウェアの互換性問題に対しては、Linuxの標準化を積極的に進めていくとし、主要なディストリビューションは既に標準に準拠している。また、WindowsのようなCertifiedロゴの導入も検討しているという。
その他には、Webのリッチクライアントアプリケーションの台頭により、OSに依存しない環境が出来上がりつつあることや、モバイル分野でのLinuxの普及が伸びていることについても触れた。
プラットフォームの品質・一貫性・パフォーマンスの改善がソフトウェアの数や市場規模の増加に繋がり、それがまたプラットフォームの向上に結びつく。このような好循環のサイクルを続けて、より一層のLinuxの普及に努めていきたいとまとめた。
この記事は参考になりましたか?
- この記事の著者
-

CodeZine編集部(コードジンヘンシュウブ)
CodeZineは、株式会社翔泳社が運営するソフトウェア開発者向けのWebメディアです。「デベロッパーの成長と課題解決に貢献するメディア」をコンセプトに、現場で役立つ最新情報を日々お届けします。
※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です