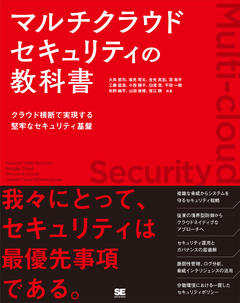本記事は『マルチクラウドセキュリティの教科書 クラウド横断で実現する堅牢なセキュリティ基盤』の「Chapter 1 マルチクラウドセキュリティの紹介」から一部を抜粋したものです。掲載にあたって編集しています。
マルチクラウドの定義と重要性
マルチクラウドの定義
マルチクラウドとは、複数のクラウドサービスプロバイダー(例:AWS、Azure、Google Cloud、OCI)を組み合わせて活用し、サービスやインフラストラクチャを管理する利用形態を指します。従来、多くの企業が単一のクラウドサービスを利用してきましたが、近年では複数のクラウドサービスを併用する企業が増えています。
マルチクラウド環境では、各クラウドサービスプロバイダーの異なるサービスや機能を活用することで、より柔軟で効率的なシステム構築が可能になります。
たとえば、AWSはスケーラビリティや豊富なサービスオプションに強みがあり、Azureは企業の既存のWindows環境と高い互換性を持ちます。また、Google Cloudはデータ解析や機械学習関連のツールが充実しており、OCIはデータベースサービスにおいて他のクラウドにはない高度な機能を提供します。
このように、各クラウドの特性を生かし、ニーズに応じた最適なサービスを選択できることがマルチクラウドの大きな魅力です。
クラウド環境の利用形態として、「マルチクラウド」と「ハイブリッドクラウド」はしばしば混同されがちですが、両者は異なる概念です。ハイブリッドクラウドはパブリッククラウドと自社で管理するオンプレミス環境を統合し、両者間でアプリケーションやデータのシームレスな運用を目指すものです。
一方、マルチクラウドは複数のクラウドプロバイダー間の連携と運用を最適化することに重点を置いており、インフラやサービスの冗長化によって業務の継続性と柔軟性を高めることを主な目的としています。

マルチクラウドの重要性
DX(デジタルトランスフォーメーション)が進む現代において、多くの企業や自治体のITインフラはますますクラウド環境に依存するようになっています。
しかし、単一のクラウドプロバイダーに依存することにはリスクもあります。クラウドサービスプロバイダーの障害やメンテナンスが発生した場合、サービスの停止やビジネスへ影響を及ぼす可能性があります。
また、機能変更や価格改定が行われることがあり、利用者側でサービス提供やコストのコントロールが困難になります。そのため、重要な業務においては複数のクラウドプロバイダーを活用することが推奨されています。
マルチクラウドの重要性は、クラウド技術の進展に伴ってますます高まっています。クラウドは進化を続け、企業のDXの中心的な役割を担っていますが、そこにはリスクやコストの課題も伴います。そのため、各クラウドプロバイダーの特性を理解し、必要な機能やサービスを適切に組み合わせたマルチクラウド戦略の構築が、今後の競争力を左右する重要な要素になると考えられます。
まとめ
今や企業のITは1つのクラウドに頼りきる時代ではありません。単一クラウドへの依存リスクを避け、複数のクラウドを併用することが、企業の競争力確保において重要性を増しています。
主要なクラウドプロバイダーの紹介
AWS
AWSは、2006年にAmazonが提供を開始したクラウドコンピューティングサービスです。Amazonのeコマース事業で蓄積されたインフラ管理ノウハウをもとに、当初はストレージサービスのAmazon Simple Storage Service(S3)やコンピューティングサービスのAmazon Elastic Compute Cloud(Amazon EC2)を提供する形でスタートしました。
その後のAWSの成長は著しく、現在は200種類を超える多種多様なサービスを持つ大規模なクラウドプラットフォームへと進化しています。以下は、AWSの主な特長です。
サービスの豊富さ
AWSはクラウドサービスの中でも最も多彩なラインアップを誇ります。コンピューティング、ストレージ、データベース、ネットワーキングからAI、機械学習、IoT、ブロックチェーンなど、各領域における専門的なサービスがそろっており、エンタープライズ向けの構築がしやすい点が特徴です。
グローバルな展開
AWSは、アジア、アメリカ、ヨーロッパ、中東など各地に数多くのリージョンを持っており、200以上の国と地域で利用可能です。とくに、企業が地理的に分散したデータセンターを使用する際の選択肢が多いため、世界中で安定したサービスの提供を実現しています。
料金体系と柔軟性
AWSは従量課金制をもとに、リザーブドインスタンスやスポットインスタンスといったさまざまな利用オプションを提供し、コストの最適化が図りやすくなっています。
AWSのセキュリティサービスとしては、AWSリソースへのアクセス権限を管理するAWS Identity and Access Management(IAM)や、暗号化を施すAWS Key Management Service(KMS)は、AWSを安全に利用するうえで必ず押さえておくべきサービスです。
2016年以降、脆弱性管理サービスのAmazon Inspector、脅威検出サービスのAmazon GuardDuty、セキュリティを包括的かつ統一的に管理するSecurity Hubなど、次々と先進的なセキュリティサービスがリリースされています。それらのセキュリティサービスで生成される膨大なセキュリティログを収集・分析可能なAmazon Security Lakeも登場し、セキュリティ管理者の業務を支援しています。
Azure
Azureは2008年に発表され、2010年から商用サービスが提供開始されました。Microsoftのエンタープライズソフトウェア分野での強力な地位を背景に、オンプレミスとクラウドのハイブリッドソリューションを得意とし、とくにWindows ServerやMicrosoft 365、Microsoft Entra IDとの親和性が高い点が強みです。以下は、Azureの主な特長です。
エンタープライズ向けの強み
AzureはMicrosoftの製品群とシームレスに統合できることから、多くのエンタープライズ企業で採用されています。とくにEntra IDやMicrosoft 365との統合により、既存のITインフラを生かしつつ、クラウドに移行することが容易です。
ハイブリッドクラウド
Azureは、オンプレミスとクラウドを連携するハイブリッドクラウドソリューションに強みを持ちます。Azure ArcやAzure Stackといったツールを活用し、ハイブリッド環境やマルチクラウド環境での統合的な管理を実現します。
グローバルネットワーク
60以上のリージョンで展開され、グローバルなサービス提供と低遅延を実現しています。
Azureは、クラウドサービスへのアクセスを一元管理するMicrosoft Entra ID(旧Azure Active Directory)をはじめ、シークレットを安全に保管するAzure Key Vault、脆弱性診断や脅威検出を提供するAzure Security Center、脅威検出から対応までを包括的に行うAzure Sentinelなどを提供しています。
2021年以降は、サービスの統廃合により、多くのセキュリティサービスが改称されました。世の中の情勢に合わせてサービスやプランが改定されることが多いため、リリースノートなどを追っておく必要があります。
Google Cloud
Google Cloudは、検索エンジンやYouTubeといった大規模なデータ処理基盤での経験を生かし、2008年にアプリケーション実行環境サービスであるApp Engineの提供をはじめとしてスタートしました。GoogleはApp Engineの提供開始以降、多数のクラウドサービスをプラットフォームに追加し続けています。とくにビッグデータ分析や機械学習に強みを持ち、データ主導のクラウドサービスとして評価されています。以下は、Google Cloudの主な特長です。
データと機械学習への強み
Google CloudはBigQueryやVertex AIといったデータ処理および機械学習サービスを提供し、大量のデータ分析を効率よく行うことが可能です。他にもビッグデータやAI / ML分野でとくに優れた機能が多くそろっています。
インフラの柔軟性と速度
Googleのプライベートファイバーネットワークを通じて低遅延・高パフォーマンスな接続を提供し、グローバルに分散されたインフラを活用した効率的な運用が可能です。
環境への配慮
Google Cloudは100%再生可能エネルギーでの運用を目指すなど、環境への配慮も評価されています。
Google Cloudは鍵管理のCloud KMS、セキュリティ状況を一元的に監視できるSecurity Command Center、脅威検出から対応までを包括的に行うChronicle Security Operationsといったサービスを提供しています。2024年にはChronicle Security OperationsがGoogle Security Operationsに改称され、生成AIによって調査や対応が効率的になりました。
OCI
OCIは、Oracleが2016年から提供するクラウドプラットフォームです。とくに、世界的なシェアを誇るエンタープライズデータベースであるOracle Databaseの長年の開発運用経験を生かし、データベースやEnterprise Resource Planning(ERP)、Supply Chain Planning(SCP)などのエンタープライズアプリケーションに特化したクラウドサービスを提供しています。以下は、OCIの主な特長です。
データベースサービスの強み
OCIはOracle Databaseの高い性能と可用性をクラウド上で提供し、とくに既存のOracleユーザーにとって魅力的なプラットフォームです。また、Oracle Autonomous Databaseなどの革新的なサービスにより、データベース管理の自動化と最適化を実現しています。
高性能なインフラ
OCIは、ベアメタルインスタンスや高度なネットワーク機能を活用した高性能なインフラを提供し、とくにハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)用途において優れたパフォーマンスを発揮します。
エンタープライズ向けの強化
ERPやSCMといったエンタープライズアプリケーションに最適化された環境を提供し、Oracleの既存製品をシームレスにクラウド上で運用するための支援が充実しています。
OCIのセキュリティサービスとしては鍵管理のKey Management、セキュリティ設定を監視するCloud Guard、脆弱性管理のVulnerability Scanning Serviceなどがあります。また、OCIは自社のデータセンターでOCIを稼働するDedicated Regionや、カスタマイズしたうえでエンドユーザーへ再販するOracle Alloyを通じて、個別のセキュリティ要件やデータ主権に対応しています。
まとめ
AWSの豊富なサービスと高い柔軟性、AzureのMicrosoft製品とのシームレスな連携、Google Cloudの高度なAIおよびデータ分析機能、OCIのデータベースに特化した強みはそれぞれの大きな特徴です。各クラウドプロバイダーの強みを見極め、目的に応じて適切な選択をすることが重要です。
主要なクラウドプロバイダーの成り立ちから考えるクラウドセキュリティの違い
クラウドセキュリティの実装には各プロバイダーがどのようにしてクラウド市場に参入し、どのような目的を持って成長してきたかが深く影響しています。このSectionでは、AWS、Azure、Google Cloud、OCIの成り立ちとその背景にあるビジョンを概観し、それぞれのセキュリティアプローチがどのように異なるかを考察します。
AWS - リーダーとしてのセキュリティ最適化
AWSは、2006年にAmazonが商業化したクラウドサービスです。もともとAmazonが社内のインフラストラクチャの効率化を目指して開発したシステムから生まれ、商業化後は迅速に市場をリードする存在へと成長しました。この背景により、AWSのセキュリティは「運用規模における効率性と柔軟性」に重点を置いた設計が特徴です。
AWSのセキュリティは顧客の多様なニーズに応じて柔軟に構成可能であり、AWS Identity and Access Management(AWS IAM)やAmazon Virtual Private Cloud(Amazon VPC)を通じて高度なアクセス制御とネットワーク分離が可能です。AWSの成り立ちを反映して、セキュリティ機能は「スケーラビリティ」と「オンデマンド性」に最適化されており、大規模なエンタープライズ顧客に対しても効率的にセキュリティリソースを提供することが可能です。
また、クラウド利用時の責任範囲を明確化した「責任共有モデル」も他社のプロバイダーよりも早い段階で明確化されています。「責任共有モデル」により、ユーザーがセキュリティ管理に対してどのような責任を負うかが明確になるため、ユーザーのセキュリティ意識向上に寄与しています。
Azure - 企業ニーズに根ざしたハイブリッド志向のセキュリティ
Azureは2010年に商用サービスとして提供が開始され、既存のWindows Serverや企業向けソリューションを基盤にしたサービスとして発展してきました。Microsoftの強みである「エンタープライズ市場向けの深い理解」と「既存IT環境との統合」がセキュリティへのアプローチに強く影響しています。
Azureのセキュリティ設計はハイブリッドクラウドへの対応に特化しており、オンプレミスのWindows環境とスムーズに統合できる点が特徴です。これにより、企業が既存のWindowsセキュリティ対策をクラウド上でも継続して活用できるようになっており、Microsoft Entra ID(旧称 Azure Active Directory)やMicrosoft Defenderなど、統合されたセキュリティサービスが提供されています。
また、Microsoftは政府機関や金融機関向けのコンプライアンスを重視し、Azure上でのセキュリティ標準を整備している点も他社と一線を画します。Azureの成り立ちが反映されているため、企業向けのセキュリティ設定が初期段階から充実しており、データ保護や認証管理において堅牢なセキュリティ対策を講じやすい特徴を持っています。
Google Cloud - データ分析とネットワークセキュリティの独自強化
Google Cloudは2008年に商用サービスとして提供が開始され、Googleのインフラを一般に提供する形で成長してきました。もともと検索エンジンやデータ分析に特化したGoogleの技術力が背景にあるため、Google Cloudはデータセキュリティとネットワークセキュリティに関して独自のアプローチを取っています。
とくに、Googleのインフラはゼロトラストセキュリティモデル「BeyondCorp」に基づいており、境界防御からアイデンティティとアクセス管理にシフトした設計が特徴です。Google Cloudは脅威インテリジェンスやAIベースの分析技術をセキュリティサービスに積極的に取り入れており、VPC Service ControlsやCloud Data Loss Preventionといったサービスで強力なデータ保護を提供しています。
Googleの成り立ちがデータの大規模分析やAI技術に強く依存していることから、セキュリティ対策においても「先進的なデータ保護」と「ネットワークの微細な管理」が主眼とされているのが大きな特徴です。
OCI - ミッションクリティカルなワークロード向けの堅牢なセキュリティ
OCIは、Oracleがミッションクリティカルなアプリケーションをクラウド上で実行するために設計したクラウドサービスです。とくに既存のデータベース顧客をターゲットに、金融機関や大規模企業のワークロードを安全に処理することを目指しており、データセキュリティの強化がOCIの基礎に組み込まれています。
OCIのセキュリティアプローチは「データベースセキュリティ」に重点が置かれており、データ暗号化、アイデンティティ管理、ログ監査などが充実しています。Oracle Databaseとのシームレスな統合により、従来のオンプレミス環境でのセキュリティ手法をそのままクラウドに移行できるよう設計されています。
またOCIは他社と異なり、主要なクラウド機能においてベアメタルインフラを採用し、物理的な分離を通じたセキュリティを実現しています。とくに金融業界や医療業界向けに、高いコンプライアンス基準に対応している点が特徴です。
まとめ
このように、主要なクラウドプロバイダーの成り立ちは、それぞれのセキュリティ戦略に直接的な影響を及ぼしています。AWSのスケーラブルなセキュリティ、Azureの企業向けハイブリッドセキュリティ、Google Cloudのデータ保護重視のゼロトラストモデル、そしてOCIのミッションクリティカルなデータ保護とベアメタルアーキテクチャは、各社の背景や顧客ニーズに基づいてカスタマイズされています。
この違いを理解することは、企業が自社のニーズに応じて最適なクラウドセキュリティ戦略を立てるうえで極めて重要です。各プロバイダーのセキュリティのアプローチを比較し、異なるセキュリティ手法の中から自社に合致するものを見極めることで、マルチクラウド環境における総合的なセキュリティ対策を強化することが可能となります。
クラウドセキュリティの基本概念
クラウドセキュリティを理解するうえで、クラウドサービスモデルとクラウド展開モデルの概念を理解することは不可欠です。このSectionでは、これらのモデルがマルチクラウド環境におけるセキュリティの確保にどのような影響を与えるかを明らかにします。
クラウドサービスモデルの種類
クラウドサービスモデルは、クラウドコンピューティングにおけるリソースの提供形態を定義するものであり、代表的なものとしてIaaS(Infrastructure as a Service)、PaaS(Platform as a Service)、SaaS(Software as a Service)の3つのモデルがあります。これらのモデルは異なる抽象度のリソースを提供し、セキュリティの責任分担がそれぞれ異なります。
1.IaaS(Infrastructure as a Service)
IaaSは仮想マシンやストレージ、ネットワークといったインフラストラクチャを提供するサービスです。利用者はオペレーティングシステム、アプリケーション、ミドルウェア、そしてデータを管理する責任を負い、プロバイダーは物理インフラストラクチャやネットワークのセキュリティを担います。
サービス例として、AWSの「Amazon EC2」、Azureの「Azure Virtual Machines」、Google Cloudの「Compute Engine」、OCIの「Virtual Machines」などが該当します。このモデルは柔軟性が高く、多様なワークロードやカスタマイズに対応可能ですが、利用者に求められるセキュリティ管理の範囲も広範です。
2.PaaS(Platform as a Service)
PaaSは、アプリケーション開発や運用に必要なプラットフォーム環境を提供するサービスです。利用者はアプリケーションコードに集中できる一方で、ミドルウェアやランタイム環境、データベースの管理はプロバイダーに委任されます。
サービス例として、AWSの「AWS Elastic Beanstalk」、Azureの「Azure App Service」、Google Cloudの「App Engine」、OCIの「WebLogic Server for OCI」などが該当します。このモデルは開発のスピードを向上させるため、ユーザーはコードの安全性やデータアクセス制御を始めとするアプリケーション層のセキュリティに注力することが求められ ます。
3.SaaS(Software as a Service)
SaaSは利用者にとって最も抽象度が高く、アプリケーションそのものをプロバイダーが提供するモデルです。ユーザーはソフトウェアをインストールせずにWebブラウザなどを通じて利用するため、プロバイダーがアプリケーションのセキュリティを包括的に管理します。
サービス例としてAWSの「Amazon WorkMail」、Azureの「Microsoft 365」、Google Cloudの「Google Workspace」、OCIの「Oracle Content and Experience Cloud」などが該当します。ユーザーはデータの利用とアクセス制御に集中することで、システム全体のセキュリティを担保します。

クラウドサービスモデルごとに、ユーザーとプロバイダーの間でどのように責任が分担されるかは「責任共有モデル」によって明示されます。各サービスモデルにおいて、利用者とプロバイダーの間で責任が異なるため、モデルごとに異なるセキュリティポリシーや対策が求められます。

クラウド展開モデルの種類
クラウドの展開モデルは、クラウド環境をどのように構築・提供するかを定義しており、以下の主要なモデルが存在します。
1.パブリッククラウド
パブリッククラウドは、AWSやAzureなどのクラウドプロバイダーが不特定多数の顧客に対してインフラを共有し提供するモデルです。コスト効率やスケーラビリティに優れていますが、同一インフラを複数の利用者が共有するため、アクセス制御やデータ保護がセキュリティ上の重要な課題となります。パブリッククラウドのセキュリティ管理は部分的にクラウドプロバイダーに委任することができます。
前述のクラウドサービスモデルごとに責任境界があるため、利用者はどのクラウドサービスモデルが該当するかを理解したうえで、適切なセキュリティ対策を実施する必要があります。本書で取り上げているAWS、Azure、Google Cloud、OCIはまさにパブリッククラウドの代表例です。
2.プライベートクラウド
プライベートクラウドは特定の組織に限定してインフラが専有されるモデルで、オンプレミスまたは専用データセンターに構築される場合が多いです。企業のポリシーに合わせたセキュリティ制御が可能であり、高度なデータ保護やコンプライアンスの要件に対応しやすい利点があります。
一方で、パブリッククラウドに比べてスケーラビリティに欠ける場合があり、管理コストが高くなりがちです。企業のデータセンターで構築される、オープンソースのOpenStackはプライベートクラウドの一例です。
3.ハイブリッドクラウド
ハイブリッドクラウドは、パブリッククラウドとプライベートクラウドの特性を組み合わせた展開モデルです。ワークロードやデータの性質に応じて適切なクラウド環境を利用できる柔軟性があるため、企業はデータセンターの拡張や災害復旧といった用途にハイブリッドクラウドを活用しています。
ただし、異なる環境間の統合とセキュリティ管理が複雑になるため、とくにデータの移動やネットワークセキュリティにおいてリスクが伴います。Azure ArcやGoogleのAnthosを活用して、パブリッククラウドとプライベートクラウドを統合管理する形態はハイブリッドクラウドと言えます。
4.コミュニティクラウド
コミュニティクラウドは、特定の業界やコミュニティのメンバーが共同で利用するために設計されたクラウドモデルです。たとえば、医療や金融などの同業者が、共通のコンプライアンス要件やセキュリティポリシーを満たすために利用することが一般的です。コミュニティクラウドは参加者間でリソースを共有しつつ、業界特有のデータ保護や規制順守の要件を統一的に管理できる利点があります。
しかし、参加者間でのポリシー整合や、クラウドの運用コストの分担などが課題となることもあります。米国政府機関向けのAWS GovCloudや教育機関向けのGoogle for Educationは、コミュニティクラウドの一例です。

まとめ
クラウドセキュリティを確保するためには、クラウドサービスモデルとクラウド展開モデルの理解が不可欠です。クラウドサービスモデルではIaaSがインフラを提供し、利用者がOperating System(以下、OS)やアプリケーションの管理を担うのに対し、PaaSではプラットフォーム環境が提供され、開発に集中できるメリットがあります。
SaaSは最も抽象度が高く、クラウドプロバイダーがアプリケーションを提供し、利用者はデータ管理に注力します。これらのモデルでは責任分担が異なるため、利用者は自身の管理範囲を明確に理解し、適切なセキュリティ対策を講じる必要があります。
一方でクラウド展開モデルは、クラウドの利用形態に応じたセキュリティ要件を考慮する必要があります。
パブリッククラウドはコスト効率とスケーラビリティに優れるものの、アクセス制御やデータ保護が課題となります。
プライベートクラウドは高度なセキュリティ制御が可能ですが、管理コストが高くなる傾向があります。
ハイブリッドクラウドは異なる環境の統合管理が求められ、とくにデータの移動やネットワークセキュリティの確保が重要です。
コミュニティクラウドは特定業界向けに最適化されていますが、運用コストやポリシーの統一が課題となることがあります。
クラウド環境ではこれらのモデルを適切に組み合わせ、責任分担を明確にしたうえで、アクセス管理、データ保護、ネットワークセキュリティ、監査対応などの対策を実施することが求められます。
とくにマルチクラウド環境では異なるプロバイダー間のセキュリティポリシーを統一し、リスクを管理することが安全で効率的なクラウド活用の鍵となります。
クラウド環境における共通のリスク
クラウドの普及に伴い、クラウドの利便性と柔軟性を享受する企業や組織が増えていますが、それに比例してセキュリティリスクも増加しています。このSectionではクラウド環境における共通のリスクに焦点を当てて、注意すべき重要なポイントを整理します。
データセキュリティ関連のリスク
クラウド環境では大量のデータがさまざまな形で保存、処理されます。また、データは物理的にクラウドプロバイダーのデータセンターに保存されるため、組織の直接的な管理範囲を超えてしまいます。これに伴い、次のようなデータ保護に関するリスクが発生します。
データ漏えい
クラウド間でデータを転送する際、適切な暗号化が施されていないと、データの盗聴や改ざんのリスクが高まります。とくにAPI経由でのデータ転送では、認証情報の適切な管理が重要です。マルチクラウド環境では異なるプロバイダー間のセキュリティ設定の差異が、さらにリスクを増幅させる要因となります。
暗号鍵の不適切な管理
暗号化されたデータのセキュリティは暗号鍵の適切な管理に依存します。鍵の紛失や漏えいはデータ復号が不可能になる、または第三者にデータを解読されるリスクを伴います。
データ転送途上における攻撃
中間者攻撃により、データ転送時に攻撃者がデータを傍受または改ざんする可能性があります。適切な暗号化プロトコルを用いた暗号化通信が不可欠です。
不完全なデータ削除
クラウドの利用において、データ削除時に適切な処理が行われていないと削除したはずのデータが残存し、不正アクセスのリスクが生じます。
偶発的なデータ公開
設定ミスやアクセス制御の不備により、本来非公開であるべきデータが誤ってインターネット上に公開される事例が多発しています。適切なアクセス制御の実装が求められます。
データ主権とコンプライアンス
各国のデータ保護法規制に対応する必要があります。たとえば、「EU一般データ保護規則」(GDPR:General Data Protection Regulation)や「カリフォルニア州消費者プライバシー法」(CCPA:California Consumer Privacy Act)といったものがあります。
これらの規制は単にデータの保存場所にとどまらず、誰が、どの国から、どのようにデータへアクセス・処理・移動するかといった運用全般に対する管理義務も含まれます。クラウドプロバイダーは複数国にまたがるデータセンターを持つため、適切な保存場所を選定することは重要です。
加えて、アクセス権の制御、越境データの移動ルール、個人情報に関する通知義務や削除請求への対応など、規制の要求事項を包括的に満たす取り組みが不可欠です。
アクセス管理・アイデンティティ関連のリスク
クラウド環境では多くのユーザーが異なる権限を持ってアクセスするため、適切なアクセス管理が重要です。不適切なアクセス管理により、次のようなリスクが生じます。
管理用インターフェースの悪用
クラウドの管理コンソールやAPIが攻撃者に狙われることがあります。クラウド環境へのアクセスに必要な認証情報(APIキー、パスワードなど)が漏えいすると、攻撃者による不正アクセスが発生する可能性があります。
とくに、認証情報がソースコード管理リポジトリや公開フォーラムで露出する事例が頻発しています。多要素認証(MFA)やIP制限を適用することで、攻撃リスクを低減できます。
アイデンティティとアクセス管理の複雑性
IDとアクセス管理機能の設定ミスが発生すると、不正アクセスや権限の過剰付与が問題になります。ロールベースアクセス制御(RBAC)や最小権限の原則の徹底が重要です。マルチクラウド環境では、プロバイダーごとに異なるアイデンティティ管理サービス(例:AWS IAM、Microsoft Entra ID、Google Cloud IAM)を使用する必要があるため、アクセス権限の管理がより煩雑になります。
この煩雑さが設定ミスを招き、結果として攻撃者が利用可能な脆弱性を生むことがあります。
クラウドプロバイダー従事者の不正
クラウドプロバイダーの内部従業員が、特権を悪用して顧客データにアクセスするリスクも考慮する必要があります。顧客による暗号鍵管理や監査ログの活用をすることで、リスクの低減が見込めます。
ネットワーク・攻撃手法関連のリスク
クラウド環境ではネットワークを通じてリソースやサービスが提供されるため、次のようなネットワークセキュリティのリスクが顕著に表れます。
不正なスキャンおよびアクセスの実施
クラウド環境は外部ネットワークに接続されているため、攻撃者による不正なスキャンおよびアクセスのリスクがあります。攻撃者はクラウド環境内の脆弱性を探すためにスキャンを実施します。
とくに、セキュリティグループやファイアウォールの設定が不適切だと、攻撃の成功確率を高めてしまいます。そのため、異常なスキャンを検知し、適切なブロックルールを設定することが求められます。
また、マルチクラウド環境ではこれらの設定を各プロバイダーで一貫して適用することが難しい場合があり、統合ツールなどを活用して一貫したルールを適用する運用が求められます。
サービスエンジンの侵害
クラウドプロバイダーが提供するサービス自体が侵害される可能性があります。ゼロトラストの考え方を適用し、外部のサービスに依存しすぎない設計が重要です。
APT攻撃
標的型の高度な持続的脅威(APT:Advanced Persistent Threat)がクラウド環境にも及ぶ可能性があります。振る舞い検知や脅威インテリジェンスの活用が求められます。
リソース・可用性関連のリスク
パブリッククラウドは、サーバーやネットワークといった共通のリソースを複数の利用者がネットワークを介して利用することが一般的です。そのため、次のようなリソースや可用性に関するリスクがあります。
リソースの枯渇
適切なリソース管理が行われていないと、リソースの枯渇によってシステムがダウンするリスクがあります。自動的にスケールをする設定や一定量のリソースを確保するなどの対応を行い、定期的にリソースを監視する運用が重要です。
DDoS攻撃
クラウドサービスを標的とした分散型サービス妨害(DDoS:Distributed Denial of Service)攻撃は、サービスの停止や遅延を引き起こします。一部のクラウドプロバイダーはDDoS対策サービスを提供していますが、設定や運用が適切でない場合、十分な防御ができないことがあります。
EDoS攻撃
経済的DoS(EDoS:Economic Denial of Service)攻撃はクラウドの従量課金モデルを悪用し、不要なコストを発生させる攻撃です。予算管理やアラート設定を活用してリスクを低減します。
設定・運用管理のリスク
クラウドは手軽に利用できるメリットがあります。そのため、設定や運用をおろそかにすると、次のような設定や運用管理上のリスクがあります。
設定ミスと不十分な変更管理
クラウド環境の設定ミスは、セキュリティインシデントが多発している主な要因の1つです。変更プロセスには変更諮問委員会(CAB:Change Advisory Board)による識者複数人でチェックすることで、ミスを防げる可能性が高まります。またクラウドの機能を活用し、自動化による設定管理や監査を実施することも有効です。
セキュアでないインターフェースやAPI
クラウドはAPIによりさまざまな処理が実施されます。APIの認証や認可が適切に設定されていない場合、攻撃者により不正利用されるリスクがあります。
不十分なクラウドセキュリティ戦略
セキュリティ戦略が不十分だと、クラウド環境全体のリスクが増大します。目的を明確にしたクラウドセキュリティ戦略や指針を策定することが大切です。また、戦略を策定した後も継続的なリスク評価が必要です。
セキュアでないサードパーティリソース
外部サービスやライブラリの脆弱性が、クラウド環境全体のセキュリティに影響を及ぼす可能性があります。どの製品を使うのかをしっかり吟味し、公式にサポートされている製品を利用するようにしましょう。
システムの脆弱性
脆弱性が存在すると、攻撃者による不正アクセス、データ窃取、運用の妨害を受ける可能性が高まります。システムやネットワークを継続的に監視し、適切にパッチ管理を行うことで、最新のセキュリティパッチを導入でき、サイバー攻撃に対する耐性を高められます。
限定的なクラウド可視性/可観測性
マルチクラウド環境ではクラウドごとに異なる可視化ツールを使用すると、クラウド環境全体の把握やインシデント対応が困難になります。クラウドプロバイダーから提供されているツールで統合的な把握が困難な場合、サードパーティツールの導入を検討することも視野に入れる必要があります。
まとめ
クラウド環境におけるセキュリティリスクは多岐にわたり、そのすべてがマルチクラウド戦略でも考慮されるべき重要な課題です。データセキュリティではデータ漏えいや暗号鍵の管理不足、転送途上での攻撃のリスクが挙げられます。
また、アクセス管理ではアイデンティティとアクセス管理(IAM)の設定ミスや、クラウドプロバイダー従業員による不正利用のリスクがあります。
ネットワーク関連では不正なスキャン、サービスエンジンの侵害、APT攻撃などが懸念されます。
リソース可用性に関しては、リソース枯渇やDDoS、EDoS攻撃などが問題となります。さらに、設定ミスや運用管理の不備もセキュリティ事故を引き起こす要因となります。
これらのリスクに対処するためには、継続的な監視とセキュリティ対策の強化が必要です。具体的な対策としては暗号化やアクセス制御の強化、監査ログの利用、適切な変更管理の実施などが求められます。クラウドセキュリティ戦略を確立し、リスク評価とポリシーの適用を徹底することで、安全なクラウド環境の運用が実現できます。
この記事で紹介したクラウド環境共通のリスクを理解して適切な対策を講じることは、セキュリティを強化し、クラウド活用の成功を確実にするための鍵となります。
マルチクラウド戦略のメリットと課題
クラウドコンピューティングが普及し、多くの企業が単一のクラウドプロバイダーに依存するリスクを軽減するために、マルチクラウド戦略を採用するケースが増えています。このSectionではマルチクラウド戦略のメリットと課題について解説します。
マルチクラウド戦略のメリット
マルチクラウド戦略とは、複数のクラウドプロバイダーのサービスを組み合わせて利用することを指します。この戦略により、企業は柔軟性、回復力、競争優位性を高められます。
1.ベンダーロックインの回避
単一のクラウドプロバイダーに依存する場合、そのプロバイダーの価格変更やサービス停止、規制変更などが企業にとって大きなリスクとなります。マルチクラウド戦略を採用することで、企業は1つのプロバイダーへの依存度を下げ、より自由にサービスを選択できるようになります。この柔軟性は、とくに規制や市場環境が急速に変化する業界において重要です。
2.高可用性と障害耐性
異なるクラウドプロバイダーのインフラを利用することで、システム全体の可用性を高められます。1つのプロバイダーで障害が発生しても、他のプロバイダーのリソースを活用することでサービスを継続できるため、事業継続性を確保しやすくなります。
3.パフォーマンス最適化
各クラウドプロバイダーは、異なる地域やサービスに特化した強みを持っています。たとえば、あるプロバイダーは特定の地域で低遅延のネットワークを提供し、別のプロバイダーは特定のAIサービスに優れている場合があります。マルチクラウド戦略を採用することで企業は目的に応じて最適なサービスを選択し、全体のパフォーマンスを向上させることができます。
4.コスト効率の向上
複数のプロバイダーを比較することで、企業はコスト効率の高いサービスを選択できます。また、プロバイダー間で価格競争が起きることにより、利用料金を抑えることも可能です。一部のワークロードをより安価なプロバイダーに移行することで、全体のコストを削減できます。
5.規制順守の柔軟性
特定の地域や業界には、データの保存場所やセキュリティ要件に関する厳しい規制があります。マルチクラウド戦略を採用することで、企業は各プロバイダーの強みを生かしつつ、規制に適合したソリューションを構築できます。
マルチクラウド戦略の課題
マルチクラウド戦略により、企業は柔軟性、回復力、競争優位性を高められますが、一方で運用やセキュリティ面での複雑さも高まります。
1.複雑な運用管理
マルチクラウド環境では、各プロバイダーのインフラやサービス、管理ツールが異なるため、運用管理が複雑になります。異なるポリシーや設定を統合する必要があるため、運用チームには広範な専門知識と経験が求められます。また、運用管理のための統合ツールやプラットフォームを導入することが必要になる場合もあります。
2.セキュリティとコンプライアンスの難しさ
各クラウドプロバイダーのセキュリティモデルや認証方式が異なるため、統一的なセキュリティポリシーの適用が難しくなります。さらに、複数の環境間でデータを移動する際には、データ漏えいや規制違反のリスクが高まります。このため、包括的なセキュリティ戦略とツールが必要です。
3.コストの管理
複数のプロバイダーを利用する場合、それぞれのサービスの利用料金を把握し、適切に管理することが課題となります。各プロバイダーが提供する料金モデルや割引プランが異なるため、コスト最適化のための分析が煩雑になります。また、不適切なリソースの使用によりコストが無駄になるリスクもあります。
4.技術的な相互運用性の課題
異なるクラウドプロバイダー間でのデータやアプリケーションの移行や統合には、多くの技術的な課題が伴います。とくにプロバイダー固有のサービスやAPIを使用している場合、他のプロバイダーで同等の機能を実現するのは困難です。このため、移行や統合を容易にするためのツールや標準化が必要です。
5.社内スキルの不足
マルチクラウド戦略を成功させるには、各クラウドプロバイダーの専門知識を持つ人材が必要です。しかし、そのような人材を確保することは容易ではなく、社内教育やトレーニングが必要となる場合があります。人材不足は、運用の効率やセキュリティの強化に影響を与える可能性があります。
マルチクラウド戦略を成功させるためのポイント
マルチクラウド戦略のメリットと課題を挙げてきましたが、これらの課題を克服して戦略を成功させるためには、適切なツールやプロセス、スキルセットの活用が欠かせません。ここでは、マルチクラウド環境を最大限に活用するために押さえるべき重要なポイントについて解説します。
1.統合プラットフォームの活用
マルチクラウド環境を管理するための統合ツールを導入し、運用の効率化と一貫性の確保を目指します。
2.包括的なセキュリティポリシーの策定
各プロバイダーにまたがる統一的なセキュリティフレームワークを構築します。
3.コスト管理ツールの導入
各プロバイダーの利用状況を可視化し、コストの最適化を行うためのツールを活用します。
4.相互運用性の確保
オープンソース技術や標準化されたツールを利用し、異なる環境間の相互運用性を高めます。
5.スキルギャップの解消
社内のトレーニングプログラムを強化し、クラウドプロバイダーごとの専門知識を持つ人材を育成します。
まとめ
マルチクラウド戦略は、企業に多くのメリットをもたらす一方で、運用の複雑化やセキュリティリスクの増加といった課題を伴います。しかし、適切なツールやプロセス、スキルセットを備えることでこれらの課題を克服し、柔軟性と競争力を最大限に引き出すことが可能です。
企業がマルチクラウド戦略を採用する際にはメリットと課題を十分に理解し、バランスの取れたアプローチを採用することが重要です。