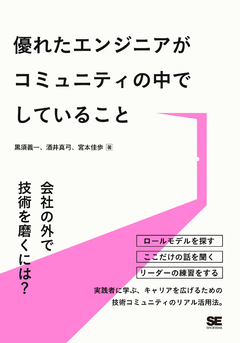本記事は『優れたエンジニアがコミュニティの中でしていること』(著者:黒須義一、酒井真弓、宮本佳歩)の「CHAPTER 3 コミュニティ活動で持っておきたいマインド」から一部を抜粋したものです。掲載にあたって編集しています。
「お作法」は必要ないが、「オープンマインド」は必要
コミュニティには、「こうあるべき」という暗黙のルールや固定観念、いわゆる「都市伝説」が存在することがあります。しかし、大前提として、コミュニティは自由な場です。
もし参加した際に、誰かから「こうするべきだ」と押し付けられる場面があったとしても、「自分にはコミュニティのルールや作法に関する知識が足りないのでは……」と気にする必要はありません。
最近では、コミュニティに関する知識やノウハウを「ビジネス」として扱う動きも増えてきました。例えば、コミュニティ運営のHow To を学ぶための有料ワークショップや、自己啓発を目的としたセミナーが開催されることもあります。これは、流動性の高い時代において、コミュニティが新たな人的資源の活用方法として注目されていることの表れともいえるでしょう。
しかし、結論からいえば、コミュニティに参加するための「ゴールデンルール」や「正解のノウハウ」などといったものは存在しません。
コミュニティは「分け合う」場
コミュニティは、好意や善意のつながりで成り立っています。基本的なスタンスは「Give and Take」――つまりお互いに情報を共有し、助け合うことです。金銭のやり取りではなく、相互の協力関係をベースとした活動こそがコミュニティの魅力です。自分が持っている知識や、他のコミュニティで得た経験があるなら、それを積極的にシェアしてみましょう。オープンな姿勢で関わることこそが、コミュニティを最大限に活かす第一歩となります。
とはいえ、関係性がまだ浅い相手に対して、自分の経験や知識をオープンにするのは難しく感じることもあるかもしれません。そんなときは、「誰かに直接伝えなければ」と気負うのではなく、コミュニティの場にそっと情報を置いていくくらいの気持ちで臨んでみてください。それが、自分自身の情報を開示するよいきっかけになることもあります。
「情報格差で勝負する人が嫌いです」、これは筆者が運営するコミュニティで、とあるエンジニアが語ってくれた言葉です。ノウハウは、独占して利益を得るためのものではなく、コミュニティの中で信頼やつながりを築くためのものです。だからこそ、惜しみなく積極的にシェアしていきましょう。必要なのは、「ノウハウを覚えること」ではなく、自分の知識や情報をシェアしようとする小さな勇気を持つことです。
「いきなりテイカー」に要注意
もう1つ、よく参加者に注意を呼びかけていることがあります。それは、「いきなりテイカー」の存在です(自分自身もそうならないように気をつけているという点で、自戒を込めたものです)。「いきなりテイカー」とは、コミュニティに対して貢献をすることなく、自分の欲しいものだけをいきなり求めて、他者の善意や好意につけ込むような人を指します。
いきなりテイカーの気質を持つ人は、ときに「どうして頼んだことをやってくれないんだ」「なんでいつも対応が遅いんだ」とコミュニティのメンバーに不満をぶつけることがあります。しかし、そもそも自分が何もGiveしていなければ、相手からのTakeを期待することはできません。相手から見れば、彼らの依頼を優先する理由がないのは当然のことです。
これは、職場でもよくある話かもしれません。何の貢献もしていないのに、見返りだけを求めても、それはうまくいきません。
よほどの有名人でもない限り、「そこにいるだけで付き合う価値がある人」などは、そうそう存在しません。だからこそ、100Giveして、ようやく1Takeできたらいい、そんな気持ちでいることが、コミュニティとの関係を築くうえではちょうどよいのです。
「正しさ・詳しさ」は必要ないが、「相互理解」は必要
技術コミュニティでは、テキストコミュニケーションにおける摩擦がしばしば生じます。特に、技術に詳しい人が質問者に対して厳しい口調で指摘したり、マウントを取ったりするようなやり取りを見かけることがあります。このような場合、双方にはそれぞれの「正義」があるように見えます。
回答者は正確な情報を伝えようとし、「少しは自分で調べてから質問してほしい」と苛立つこともあるでしょう。一方で、質問者の立場からすれば、「そもそも何がわからないのかがわからない」状態であることも少なくありません。では、コミュニティに参加するうえで、「正確な知識」や「技術に対する詳しさ」ははじめから必要なのでしょうか?
答えはNOです。コミュニティは活動への参加を通じて、学び、成長していく場です。最初から知識が十分でなくても問題はなく、むしろコミュニケーションの中で詳しくなっていけばよいのです。だからこそ、間違った情報を発信している人を見かけたときには、ただ咎めるのではなく、冷静に誤りを指摘し、正しい情報を共有することが大切です。その姿勢こそが、コミュニティ全体の成長につながります。
ただし、質問する側が前述したいきなりテイカーのような人だったとしたら、その苛立ちは正しいものです。質問する側も誠意を持って、感謝と自分にできるGiveを考えながらコミュニケーションすることが必要でしょう。
「質問」は「対話」の入り口
コミュニティにおいて、質問は必ずしも厳密な正解を求めるものではありません。それよりも、質問を通じて対話が生まれ、相互理解が深まることこそが重要です。質問に対して真摯に向き合い、さまざまな意見が飛び交う中で、参加者それぞれが学びを得られる場となることが、コミュニティの本来の姿といえるでしょう。
もし間違いがあれば、それを指摘するのではなく、共に正していくプロセスを楽しめばよいのです。その過程で得られる気づきは、個人だけでなく、コミュニティ全体の学びにもつながります。コロナ禍を経て、対面のやり取りが減り、テキストやオンラインツールを活用したコミュニケーションが急増しました。
こうした変化はまだ歴史が浅く、多くの人にとって当たり前のものではありません。だからこそ、「場」が変わったこと、「参加者が多様であること」、そして「求められているのは正解ではなく、対話であること」を意識することが大切です。
「お金」は必要ないが、「時間」は必要
基本的にコミュニティへの参加に費用は必要ありません(一部、会費を徴収しているコミュニティも存在します)。それよりも圧倒的に必要になるコストは「時間」です。コミュニティで活動するための時間は、プライベートや業務の合間から捻出することになります。限りある時間をどれだけコミュニティへ差し出すのかという点は、人によって価値観が分かれるところです。
筆者は、コミュニティ活動のために自分の時間が圧迫されてしまうことは、ある程度覚悟しておく必要があると考えています。時間的なコストを払う必要があることを理解せずに、「コミュニティに入れば何かよいことが起こるはず」と安易に参加してしまった結果、うまく馴染めずに思い悩んでしまう人は少なくありません。個人的には、こういった「思っていたのと違う」という不幸なミスマッチは減らしていきたいと考えています。
コミュニティの時間をどう捉えるか?
コミュニティ活動の時間をいかに捻出するかという視点でいえば、皆さんはプライベートと仕事の時間を区別すること、いわゆる「ワーク・ライフ・バランス」という言葉に対してどのような印象を持っているでしょうか。筆者は、常々この言葉を「ワーク・イン・ライフ」に置き換えて考えるとしっくり来ると感じています。
ワーク・イン・ライフとは、働くことが人生の一部であることを意識し、仕事と生活が一体となって満たされていく生き方を指す考え方です。仕事と生活を適切に調整し、互いが良好な関係を保つ状態を指しているワーク・ライフ・バランスとは異なり、仕事と生活は「対立・分離するものではない」という視点が前提にあります。
これは、コミュニティのための時間を考慮する上でも応用できます。「コミュニティ・ワーク・ライフ・バランス」のように、コミュニティ活動に必要な時間、仕事に必要な時間、プライベートに必要な時間をそれぞれ独立して整えようとすると、調整していく対象が3つに増え、窮屈さを感じてしまうでしょう。
一方で、「コミュニティ・イン・ライフ」「ワーク・イン・ライフ」のような考え方に切り替えてみると、コミュニティもワークもライフ(人生)の一部であり、人生を豊かにしていくうえでどれも必要不可欠なものと感じられるはずです。コミュニティへの関わり方に正解はありません。「限られた時間の中で、どう関わるのが自分にとってベストなのか?」を考えながら、自分なりのスタンスを見つけていくことが大切です。時間を「奪われる」ではなく、「時間をどう使うか」という視点で考えてみることをおすすめします。
「実績」は必要ないが、「事例」は必要
あなたがこれから参加しようとしているコミュニティの運営者や、他の参加者は、あなたに何を求めるでしょうか。例えば、あなたが特定技術分野の権威であったとして、その肩書や実績はコミュニティ活動の上で不可欠なものでしょうか。答えは「あると嬉しい(Nice to Have)が、必須(Must)ではない」です。
それよりもはるかに重宝されるのは、実際にあなたが業務で経験した技術的な課題や失敗談、それを乗り越えた経験や工夫などの事例です。「あなたが何者であるのか」はさほど重要ではなく、「どんな経験を語れるか」がコミュニティでは価値を持ちます。
“いつメン”持ち回りコミュニティの憂鬱
これは参加するコミュニティを選ぶ段階でも重要な視点です。参加者の肩書や実績ではなく、個人が持つさまざまな経験や事例にフォーカスし、スポットライトをあてているようなコミュニティを見定めるようにしましょう。
以前、登壇者がいつも同じレジェンドばかりになっていたコミュニティに参加していたことがあります。登壇する面々はいわゆる“いつメン”(いつものメンバー)であり、毎回同じような話を繰り返すばかりで学びもありません。そこにあるのは「何やらすごそうなこと、ありがたそうなことを言っているな」という権威でデフォルメされたコンテンツです。いつしかそのコミュニティからは足が遠のいてしまいました。
皆さんも、コミュニティを選ぶ際には、そのような権威に振り回されていない、参加者をフラットに評価しているコミュニティを選択することをおすすめします。
「懇親会」は必要ないが、「好奇心」は必要
コミュニティでは、イベント終了後にしばしば「懇親会」が開催されることがあります。懇親会は、イベントに参加したエンジニア同士で交流を深める場として設けられ、時にはアルコールや軽食も振る舞われて小規模な立食パーティのようになることも多くあります。筆者は普段、コミュニティ運営者として懇親会をセットしておきながら、このイベント後の懇親会というものが非常に苦手でした。もともと人見知りということもあり、次のような苦い思い出が残っています。
- 毎回の自己紹介に疲れてしまう
- ほぼ初対面の人とのコミュニケーションが疲れてしまう
- 気がつくとぽつんと1人ぼっちになってしまう
もちろん、懇親会に参加しなくとも、コミュニティ内で交流を深めることは可能です。筆者が運営するJagu'e'rは、コロナ禍に立ち上がり、コミュニケーションのすべてをオンラインで完結させてきました。それでも、参加者同士の関係性が深まっていく様子を何度も見てきました。コロナ禍以前、オフライン開催が主流だったコミュニティ界隈では、懇親会に参加して交流を深めるべし、という呪縛があったように思います。しかし本来、懇親会もMustではなくNice to Haveなのです。
大切なのは、他者への「好奇心」
懇親会に参加する/しないにかかわらず、コミュニティに参加する際に持っておいたほうがよいマインドがあります。それは「他者への好奇心を持つこと」です。他者への好奇心は、次のような素朴な疑問から始まります。
- あの人はどういう人なんだろう
- 何を大事にして生きているんだろう
- 好きなことはなんだろう
- どんなことで笑うのだろう
- どんなことで怒るのだろう
「他人に興味関心を持とう」と意識しても、その実践はなかなか難しいことです。しかし、一度その方法論が自分の中で確立できれば、大きな武器になります。他者に興味を持つことで、自分との比較が正確に行えますし、コミュニケーションや交流にプラスの影響をもたらします。
その効果はコミュニティのみならず、職場やプライベート、人生のあらゆる場面で役立つでしょう。だからこそ、コミュニティで「他者への好奇心を育てる練習をしよう」くらいの気持ちで臨んでみることをおすすめします。