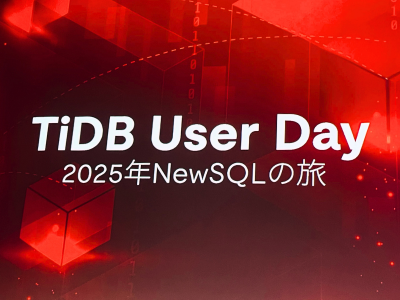いいAI機能でもデータがなければうまく動かない
いざ実務で使おうとすると、今度は検索したいデータがそもそも登録されていない問題に遭遇した。例えば本人の志向や希望も加味して検索したいが、「異動OK」のフラグはあっても、具体的に何をしたいかの情報がない。あるいは実務経験に応じて検索したいが、大まかな仕事内容しか分からず細かいタスクレベルの情報がない。
データを増やすための解決策の1つとして、従業員が自らデータを登録したくなるような機能を開発することにした。従業員それぞれのための「マイページ」にて過去の経験や今後の希望についての入力をうながす機能だ。入力した内容に応じて、AIがマッチする学習コンテンツを提示。目標となるロールモデルを登録していれば「こういうスキルをつけるといい。こういう経験を積むとよい」と提案してくれる。情報を登録することで従業員は有益な情報を受け取ることができるため、入力を促せる。もともと従業員の情報収集に苦労している企業は多いため、この機能はお客さまからも好評だった。
入力された情報に対するサジェストにも生成AIを使用している。ロールモデルに関するサジェストでは、対象の従業員の要約とロールモデルに指定された従業員の要約を取得し、Geminiに与えてどのようなスキルをつけたほうがいいかを生成させる。
吉田氏は「よいAI機能を作っても、データがなければうまく動きません。データを集めるための工夫はAI機能を作る上では必須です」と強調する。
AIコスト可視化はクラウドベンダーが用意している機能を活用
お客さまの利用が増えてくると、クラウド費用のなかで生成AIコストが占める割合が増えてきた。「COMPANY Talent Management」シリーズはマルチテナント構成なので全体でかかるコストしか分からなかったが、ビジネス側からの「テナントごとの生成AIコストを知りたい」という要求に対応する必要が出てきた。
この問題の対処は比較的シンプルに解決できる。AWSならAmazon Bedrockのアプリケーション推論プロファイルを使う。テナントごとのコスト配分タグを追加すると、マネジメントコンソールでテナントIDごとにかかったコストを表示できる。Googleも似たような形で、ラベルを使うことでテナントごとのコスト配分タグを追加すると、コンソールでコストを表示できる。

最後に吉田氏は、「生成AIをとりまく環境は日々進化しています。特にモデル選定の部分は状況が変化していて、現時点ではベストな選択は別にあるかもしれませんが、あくまで事例として参考になれば幸いです」と述べ、セッションを締めくくった。