「汎用性の高さ」と「エンジニアとしての評価」は反比例?
エンジニアのキャリアパスは領域別に分かれていたり、フルスタックな方向性があったりと実に十人十色だ。なおかつ、同じ名前で呼ばれる職種(SREなど)であっても、会社によって担当範囲は異なることから、キャリアパスのベストプラクティスを定義することは非常に難しい。
自らを「”広く浅く”で歩んできた」と表現する川崎氏は、SREや社内情報システム、セキュリティのエンジニアリングマネージャーに至るまで数多くの職域で活躍してきた。そんな川崎氏は、キャリア形成にあたって3つの大きな課題に直面したという。

1点目はキャリアの方向性が定まりにくい点だ。エンジニアとしての汎用性を高める方向に舵を切ったキャリアの広げ方は、「いろいろできる人」として高く評価される一方で、場合によっては「器用貧乏」なのではないか?と疑心暗鬼に陥ってしまう。
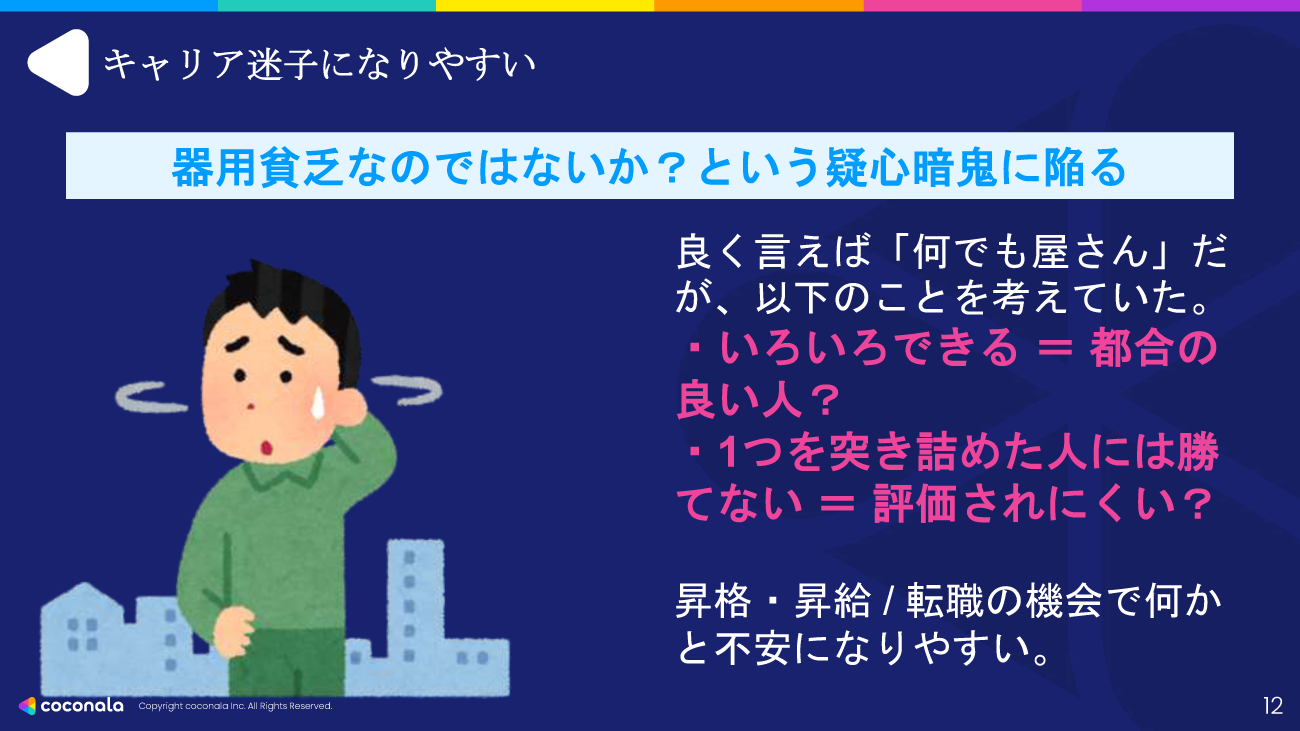
またこうしたエンジニアにとっては、1つの分野を突き詰めた専門家と比較して、技術力の面で評価されにくいという問題もある。突出した強みがないことで、昇給や昇格、転職時の評価において不安を感じやすいのだ。
2点目はロールモデルの設定が困難な点だ。エンジニア業界では「狭く深く」というキャリアパスが一般的であり、ココナラの社内外を見渡しても、「広く浅く」型のロールモデルとなる人材は決して多くなかった。
開発においては「TTP(徹底的にパクる)」を信条とする川崎氏だが、“広く浅いキャリア”においては“パクれる”対象が限られ、先人の「いいとこ取り」がしにくいという悩みがあった。
3点目はマネージャーポジションの獲得における課題だ。マネージャーポジションを得るには、既存マネージャーの昇格、もしくは交代によるアサインを待つか、新規ポジションを創出するか、といった道筋があるが、一点特化型の人材と比較すると、汎用性の高いエンジニアは会社からのプレゼンスや評価において不利な立場に置かれやすい。
「広い領域で立ち回れるエンジニアは組織にとって重要ではあるものの、トップレベルのスキルや知見を持ち合わせていないと思われがちだ。その結果、”いたら助かるが、いなくても大丈夫”と思われがちだ」。川崎氏は、自身の苦い経験からそう語る。
















































