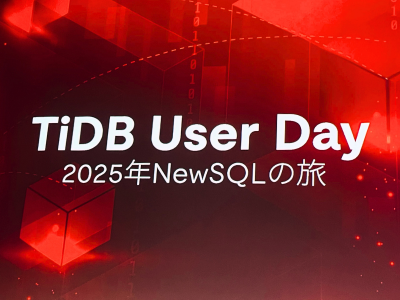ダウンロード サンプルファイル (675.1 KB)
会員登録無料すると、続きをお読みいただけます
- 修正履歴
-
- 2007/01/15 10:09 誤字修正:Allow Hardware Ccceleration → Allow Hardware Acceleration
- 2006/08/28 10:02 FileMonのリンク先を修正
- 2006/05/24 11:12 高萩さん(とっちゃんさん)のblogへのリンクを再度更新。
- 2006/05/23 19:35 高萩さん(とっちゃんさん)のblogへのリンクを更新。
- 2006/02/07 16:06 Visual C++ 2005 Express EditionでPlatform SDKを使うための設定紹介を、MSDN日本語版のページから高萩さん(とっちゃんさん)のblogに変更。 当初TLSにコールバック機構は存在しないと書いていたが、TLS Callbackが存在することが分かったため訂正。
- 2005/12/23 03:44 コラム10の用語ミスを修正。
- 2005/12/23 03:39 図2のコメントが間違っていたのを修正。 コラム3の「前者」が何を指すか分かりにくい箇所に表現を補う。 コラム10の説明を大幅に見直し。
- 2005/12/20 14:14 「コラム1 DirectXランタイムライブラリ」にてD3D_DEBUG_INFO使用時の表現に不正確な点があったのを修正。
- 2005/12/20 11:45 「Hook関数の使い方」で記事とサンプルコードで一致していなかった箇所を修正。 コラム「マルチスレッドCRT」で文体を統一するための修正。
この記事は参考になりましたか?
- この記事の著者
-

NyaRuRu(ニャルル)
趣味としてDirectXを嗜んでいたところをMicrosoft MVPとして拾われる。Microsoft MVP for DirectX (Jan 2004-Dec 2006) ここしばらく.NETに浮気中.
※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です