大企業のビジネスを成功に導くシステム構造とは?
次に、サービスの構成を見てみよう。明治エコシステムは、複数のサービスをマルチプロダクトで展開していくため、巨大なモノリスをワンチームで開発・運用するのは現実的ではない。システムが複雑になるので認知負荷が高まり、コミュニケーションも肥大化してしまうからだ。
そのため、以下のような形で、明治会員IDやデータウェアハウス、CRMなどの基盤システムは、それぞれ独立したサービスとして運用されている。システムごとにチームが異なるのはもちろん、データベースやプログラミング言語も異なるし、内製と外注も混在している。それぞれのサービスはAPIで連携し、必要に応じて情報をやり取りする仕組みになっている。

ここに辿り着くまでに、木下氏は「システムの設計とは、分断の設計である」ということに気がついた。なぜなら、人の集団は無意識に線引きをして分断するものだからだ。そして分断が生まれると、コンフリクトが生じ、コミュニケーションコストが上がる。それならば、「意図的に分断する、つまり分断をデザインする発想を持つべきだ」というのが木下氏の主張である。
そこで、「望ましいシステム構造に合わせて組織を設計する」という逆コンウェイ戦略のように、「望ましいシステム構造に合わせて境界線を引き、分断をデザインしてみよう」と考えた。
ここで問題になるのが、「望ましいシステム構造とは何なのか?」ということだ。開発効率が良い?エンジニアが働きやすい?メンテナンスがしやすい?拡張しやすい?しかし、それらはいずれも本質的ではない。ビジネスをするために集まっている以上、「ビジネスの成功にもっとも貢献できること」が望ましいシステム構造だと言えるだろう。
そこで明治エコシステムでは、ビジネスチームのインセンティブ構造に沿って、“意味の境界”でシステムを切り分けることにした。まずは「各事業のKGI/KPIを最大化したい」という要望と、「クロスユースを促して明治LTVを最大化したい」という要望で分けた。さらに、前者はそれぞれのサービスで切り分け、後者は「情報を集約したい」「横につなげたい」という要望に応じて、以下のようなシステム構成に切り分けた。







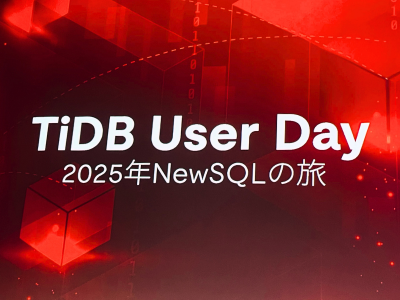

















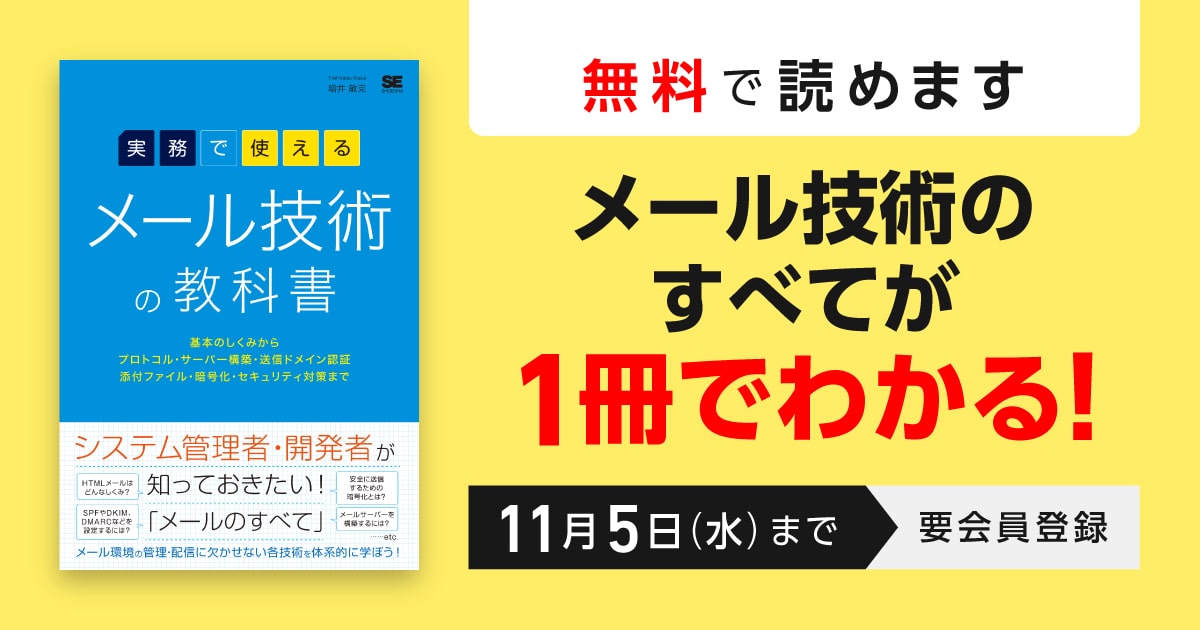
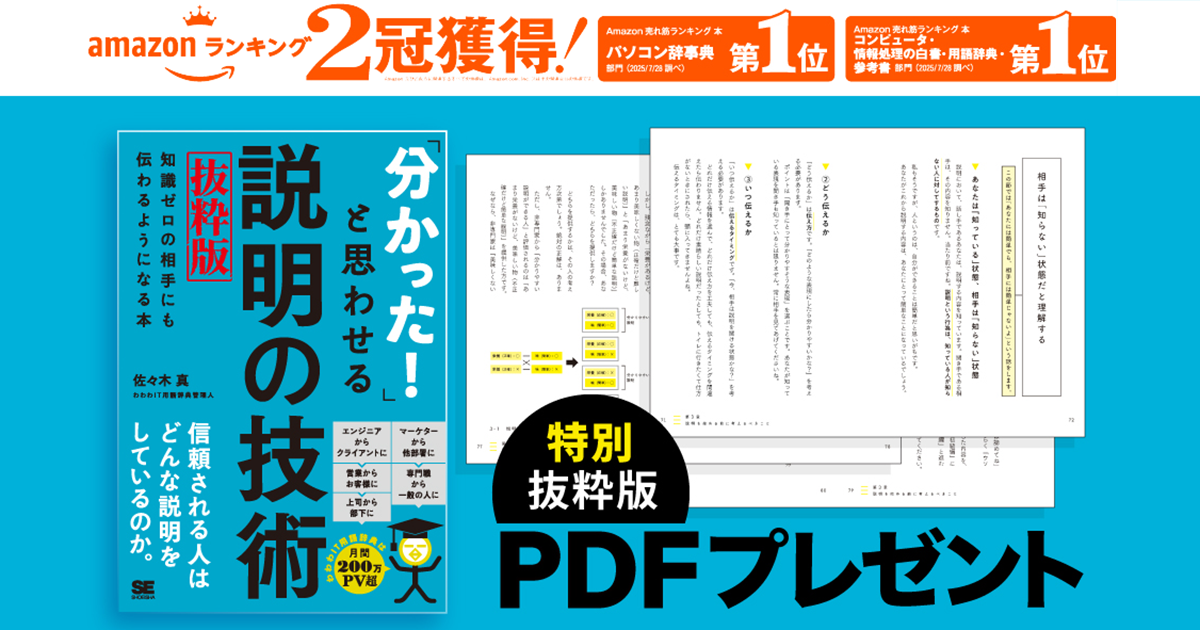








.png)














