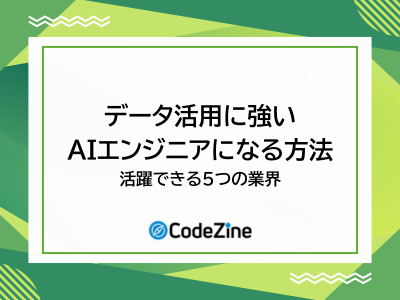「データテクノロジー」に関する記事
123件中1~20件を表示
-
データ活用に強いAIエンジニアになる方法 活躍できる5つの業界
AIが社会を根底から変えつつある今、AIエンジニアは未来を創るキーパーソンです。AIエンジニアは単なる技術者ではありません。膨大なデータを駆使...
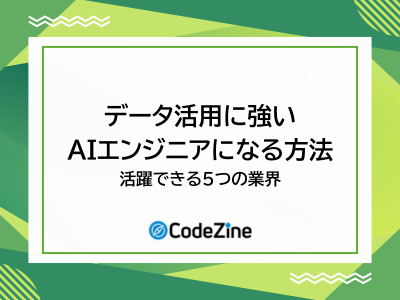 0
0 -
SOMPOホールディングスはデータにどう向き合うのか? データ統合プロジェクトのリアルに迫る
組織の規模が大きくなればなるほど、データの一貫性・信頼性を担保する仕組みの構築は、至難の業となる。SOMPOホールディングスではそんな「唯一の...
 7
7 -
計測と改善をひたすら繰り返したら、年間コストを1億円削減した──不確実性の高いプロジェクトに挑む
見込みも立てにくい難しいプロジェクトを始めると、開発現場が迷走し、いつまで経ってもシステムが完成しないということがままある。完成したとしても、...
 3
3 -
LLMの日本語能力は? リーダーボード「Nejumi.ai」の開発・運営から見えてきた課題
ChatGPTをはじめ、オープンに利用できる大規模言語モデル(LLM)が続々と公開される中、これらの日本語能力はどれほどのものなのだろうか。本...
 6
6 -
DataOpsとは何か? データサイエンティストが最大の価値を発揮するための戦略と方法論
膨大なデータを収集・分析しビジネスに活かす。データ活用の文脈でよく使われる言い回しですが、実現するとなると途方もなく難しいプロジェクトです。多...
 0
0
123件中1~20件を表示





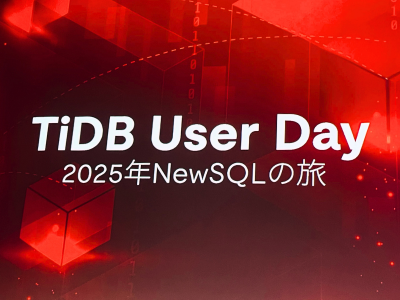















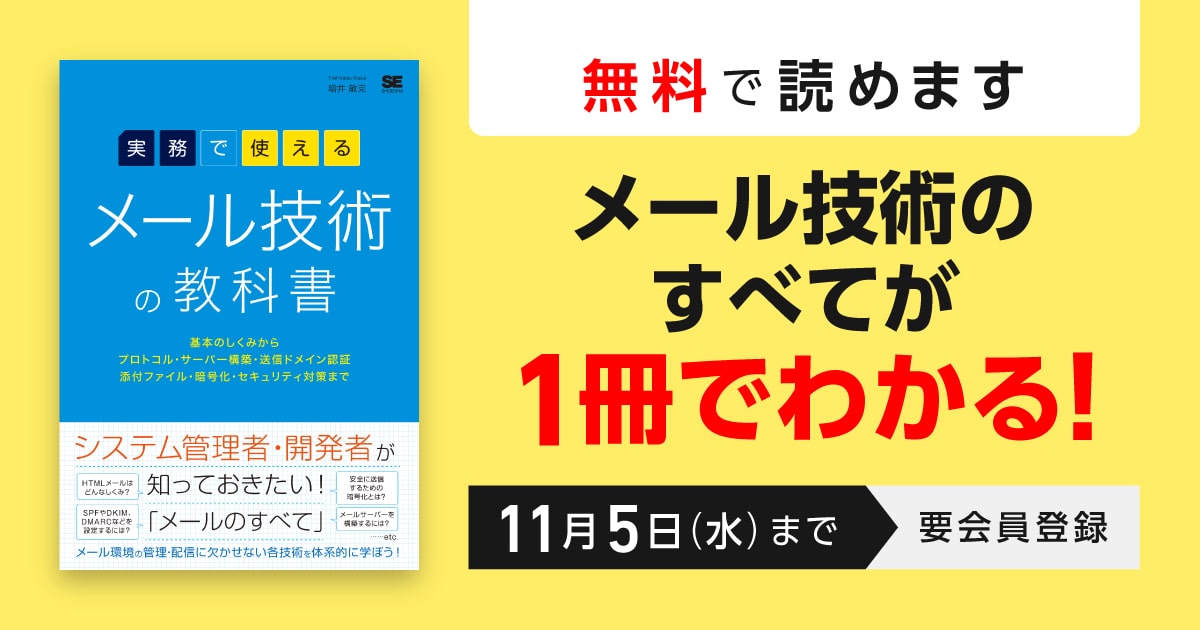
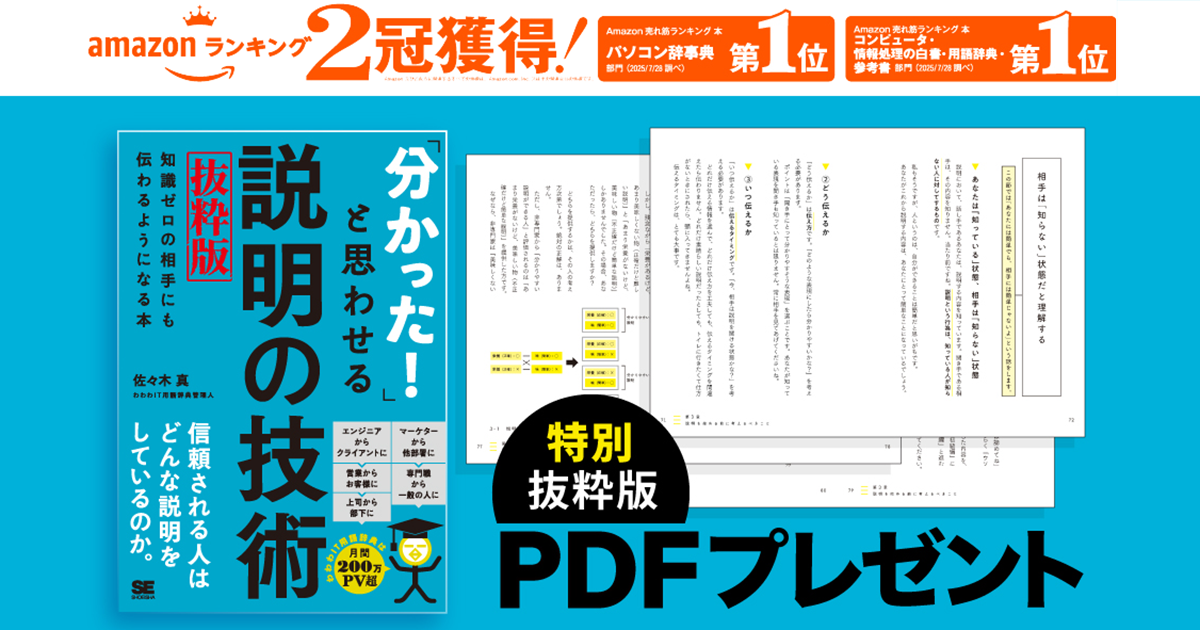









.png)