技術トレンドの波を乗りこなす「目利きの極意」
──この25年間、オープンシステム、クラウド、AIと大きな技術の波が訪れました。経営者でありながら現役エンジニアでもある漆原さんは、どう技術の価値を見極め、ビジネスに取り入れてきたのでしょうか?
ポイントは2つあります。1つは「絶対に自分で触る」こと。もう1つは、それを作っている開発者に直接会いに行き、彼らがどういう思いやスキルで取り組んでいるのかを正しく見ることです。
まず、触ってみないと肌感覚が分かりません。ただ、触っただけではまだ未熟な技術もあります。しかし、開発者に会って話を聞けば、「この人たちであれば間違いなく伸びる」と直接見て分かるのです。クラウドも同様で、AWS Japanができる前から取り組んでいましたが、それは開発者と話をして、どのような投資をし、どのような技術チームで取り組んでいるかを見れば「明らかにこうなる」と分かったからです。AIも同じです。
──最近発表された、自律型AIエンジニア「Devin」との提携も同じプロセスだったのでしょうか?
はい、そうです。Devinを実際に使ってみて「これは異次元の、本当にゲームチェンジャーになるかもしれない」と感じました。それは会って話してみないと分からないので、「ぜひ会いたい」と積極的にコンタクトを取りました。
生成AI技術は、実は最も成果が出るのは、私たちソフトウェアエンジニアリングの領域なのです。そのトレンドがエージェントという形になり、より高度な世界に進むのであれば、そうした技術が登場して然るべきだと考えていました。そして、メンバーに会って話をすれば、技術屋なので分かります。彼らは最高です。
──Devinのチームに「本物だ」と確信した決め手は何でしたか?
CEOのスコット・ウー氏のような天才的な人物がいて、その周りには競技プログラミングのトップランカーのような開発者のネットワークやコミュニティが存在します。そうした人たちが集まって会社を作っている。そのコミュニティや技術者のネットワークの中で、誰の技術が本物で、どのようなチームなのかを見極めることが極めて重要です。彼らが私たちの会社に遊びに来たとき、7×7×7のルービックキューブで遊んでいるのを見て、「こいつらは本物だ」と確信しました。プロトコルが同じ、という感覚です。

「エンジニアよ、起業せよ」「一生エンジニアであれ」──2つのメッセージの真意
──漆原さんは「エンジニアは起業すべきだ」と「一生エンジニアでいよう」という、一見矛盾する2つのメッセージを発信されています。その真意を教えてください。
私が言いたいことは2つだけです。1つ目の「エンジニアは起業しよう」というのは、ビジネスサイド、特に経営にエンジニアがしっかりと関わっていくべきだ、ということです。エンジニアだからこそ見えるビジネス、できるマネジメントがあるはずです。
そしてもう1つの「一生エンジニアで食っていこう」というのは、技術屋として技術から離れない、ということです。私にとってはこの2つは全く矛盾しておらず、両方を兼ね備えているべきだと考えています。技術が分かる人がテックカンパニーを率いるからこそ、うまくいく時代になってきているのです。
──AIの時代になり、マネジメントのあり方も変わっていくのでしょうか?
はい。特にAI駆動開発がここまで来た今、旧来型のマネジメントは不要になります。言われたことだけを作る人も、人手で穴を埋めるような働き方も、いずれはAIエージェントに置き換えられます。それはもはやキャリアですらない。だからこそ、ますます面白い時代になり、より重要で価値の高い仕事ができるようになるはずです。これまでのマネジメントは、感情のコントロールといった人間的な難しさがありましたが、AIエージェント相手にはそうしたストレスはなくなり、むしろ論理性が求められます。
──漆原さんが考える「エンジニアだからこその経営」とはどのようなものでしょうか?
技術の価値や可能性を理解し、自分で作れる、あるいは言ったことを実現できること。その上で、それが世の中にどういう価値を生むかを具現化し、最終的にビジネスの結果を出せる人です。技術屋でなければ、その価値を正しく活用できない時代になってきています。
これまで主流だった人月ベースの見積もりは、そろそろ終焉させるべきです。技術者の価値は人数だけでは測れない。これから面白い世の中になると思います。





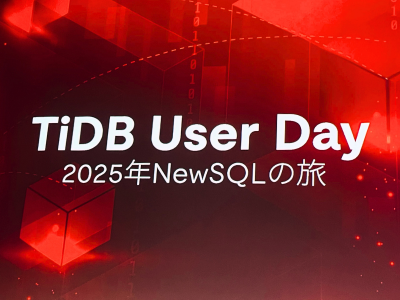
























.png)














