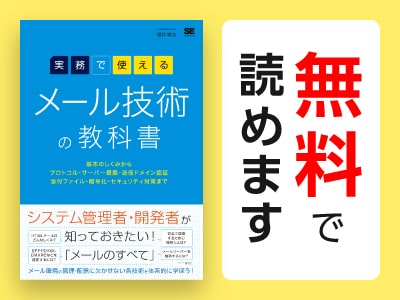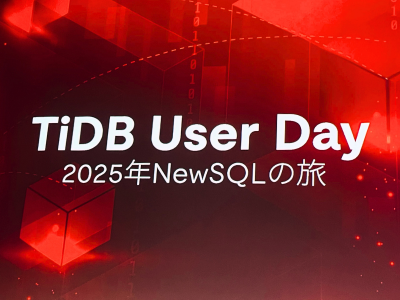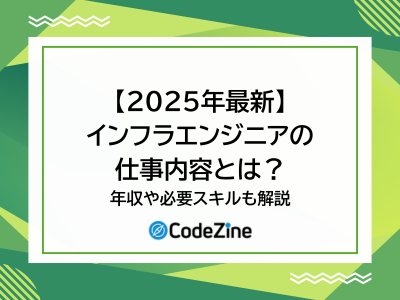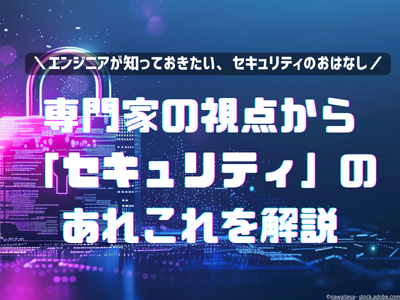「インフラ」に関する記事とニュース
-
AI時代に求められるデータベースの選択──PingCAP CEOが語る開発速度と事業成長を左右する戦略資産
AI支援開発ツールの普及により、開発速度は劇的に向上している。しかし、この恩恵を最大限に引き出せている企業は多くない。アプリケーション層の開発...
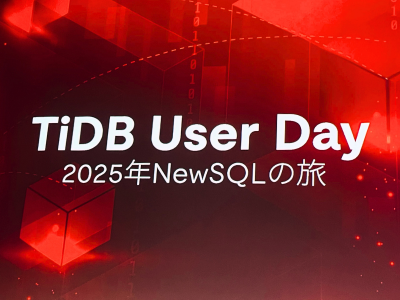 1
1 -
【2025年最新】インフラエンジニアの仕事内容とは?年収や必要スキルも解説
デジタル化が進む現代社会で、ITインフラはサービスやビジネスを支える不可欠な基盤です。インフラエンジニアは、この重要な基盤の設計から運用までを...
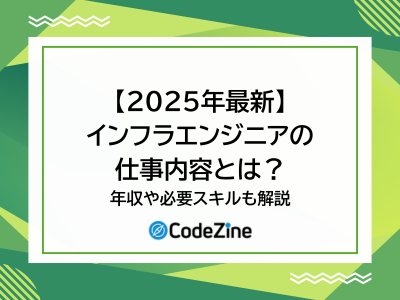 2
2 -
「孤軍奮闘するエース」のためのIaC×Observability入門──東京エレクトロンデバイスが示すツール導入にとどまらない可能性
インフラ運用が特定の担当者に依存し、構成や状態がブラックボックス化してしまう──多くの開発組織が直面するこの課題に対し、東京エレクトロンデバイ...
 1
1 -
【最近の脅威事例から学ぶセキュリティ】ネット証券を狙ったインフォスティーラーって何?
証券会社への不正アクセス事件で注目を集めた「インフォスティーラー」。このマルウェアはブラウザに保存された認証情報を狙う新たな脅威です。多くの専...
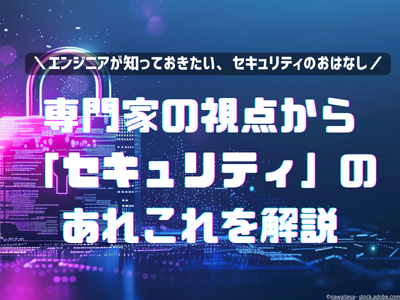 5
5
233件中1~20件を表示