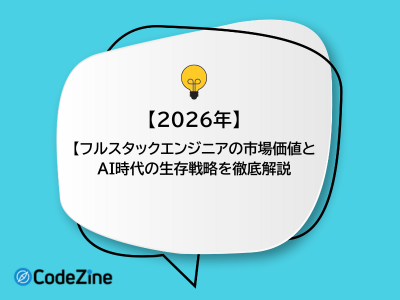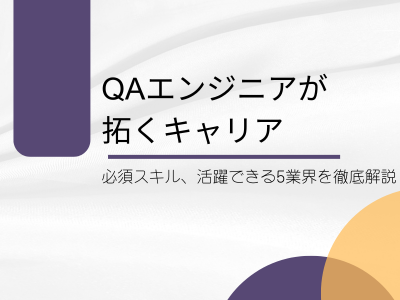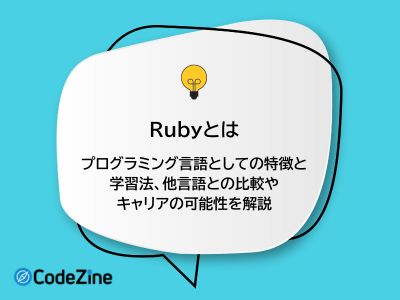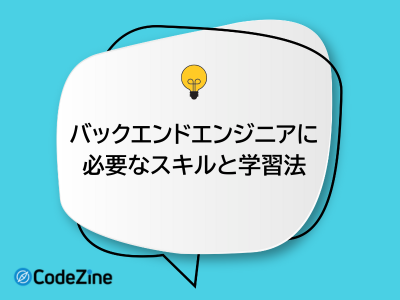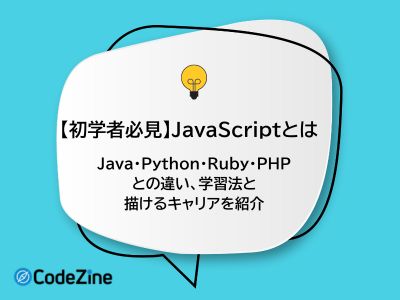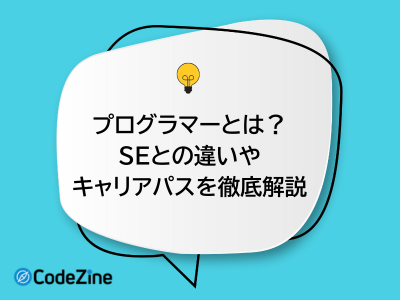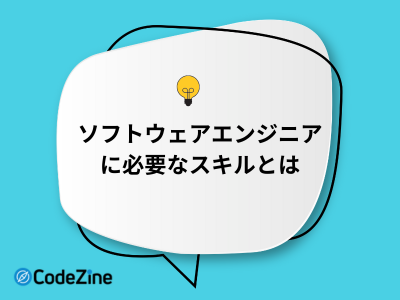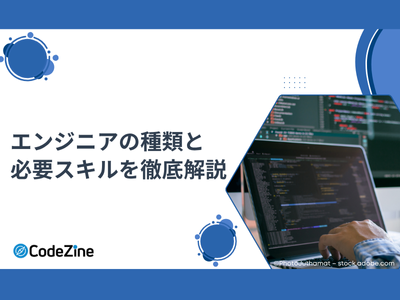「キャリア」に関する記事とニュース
-
「品質」を突き詰めた先に「マネジメント」があった──QA出身のエンジニアリングマネージャー miisanのキャリア
エンジニアとしてのキャリアパスが多様化する現代において、ロールモデルを見つけることは容易ではない。株式会社カケハシの小田中育生氏がホストを務め...
 1
1 -
【2026年】フルスタックエンジニアの市場価値とAI時代の生存戦略を徹底解説
AI技術の急速な進化により、システム開発の現場は劇的な変革期を迎えています。「AIの進化により、フロントエンドエンジニアは不要になる」といった...
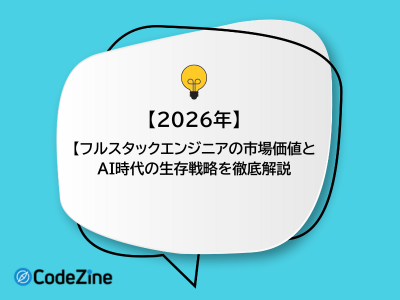 1
1 -
「何に向いているか分からない」エンジニアへ──適性に応じてキャリアを選択できる【メシウス】の働き方
1980年に創業し、「常に謙虚さを持ち、しなやかな思考で、お客さまの期待と信頼に応え続ける」という経営理念のもと、帳票開発コンポーネント「Ac...
 4
4 -
QAエンジニアが拓くキャリア 必須スキル、活躍できる5業界を徹底解説
QAエンジニアは、単なるバグ発見者ではなく、開発プロセス全体を牽引し、製品の品質とビジネスの成功を保証する戦略的な専門家です。本記事では、開発...
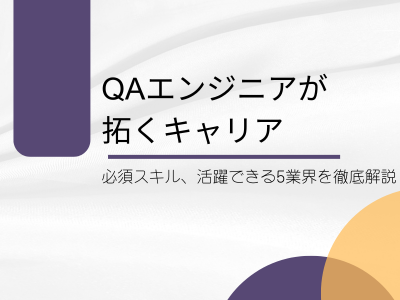 1
1 -
Rubyとは プログラミング言語としての特徴と学習法、他言語との比較やキャリアの可能性を解説
プログラミング言語Rubyの基礎から学べるリソース、勉強法、習得のメリット、他の言語との違いを詳しく解説。初心者にも最適なガイドとなっています...
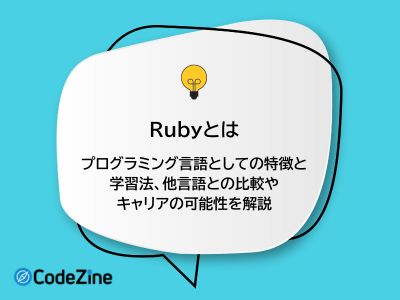 0
0 -
デジタルサービスの根幹を支えるバックエンドエンジニア。Webアプリケーションの機能やデータを管理し、ユーザーの目には見えない部分でサービスの安...
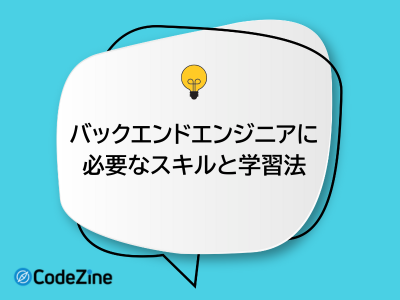 11
11 -
【初学者必見】JavaScriptとは Java・Python・Ruby・PHPとの違い、学習法と描けるキャリアを紹介
JavaScriptの基本からJava・Python・Ruby・PHPといった他言語との違い、効率的な学習法や情報収集方法、描けるキャリアにつ...
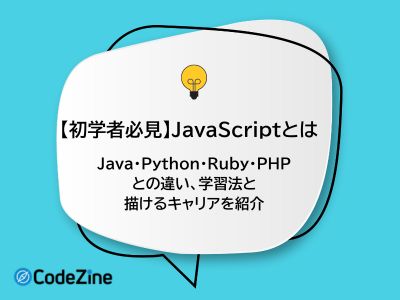 1
1 -
プログラミングと聞いて、どのような仕事を想像しますか? 一日中パソコンに向き合ってコードを書いている姿でしょうか。もちろんそれもプログラマーの...
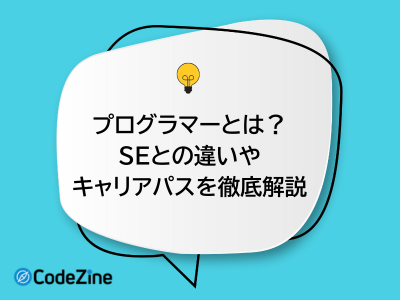 1
1 -
ソフトウェア開発分野におけるキャリアを検討されている方、または現職のエンジニアとしてスキルアップを目指している方に向け、本記事では「ソフトウェ...
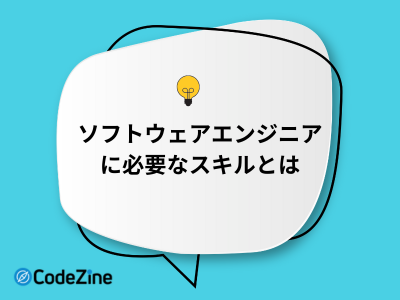 1
1 -
「エンジニア」という言葉を耳にしない日はありませんが、その多様な種類や具体的な仕事内容、未経験から目指せるのかなど、疑問を抱く方も多いでしょう...
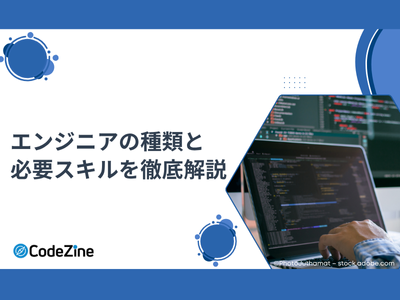 0
0 -
現場と上流の往復で見つけた「構造」という武器──アーキテクト 尾髙敏之さんが語る、事業目線の育て方
成長過程にあるエンジニアにとって、「アーキテクト」という職種は憧れの存在である一方、その実態やキャリアパスは見えにくい。技術選定のスペシャリス...
 7
7 -
残業が0でも生産性5倍に!全社AI導入を推進するジーニー・CTOが語る次世代エンジニア像と組織のあり方とは?
近年、目覚ましい勢いで進化を続ける生成AI。多くの企業がその導入を検討する一方で、エンジニアの中には生成AIとの連携方法に苦慮する人も少なくな...
 27
27 -
アーキテクトは「価値」と「勝ち」を設計する──アーキテクト 米久保剛さんが語る、技術とビジネスをつなぐ思考
成長過程にあるエンジニアにとって、数年後の将来像を想像することは難しい。本連載「エンジニアキャリア図鑑」は、カケハシの小田中育生氏が、さまざま...
 3
3 -
フロントエンドエンジニアの役割とは?バックエンドとの違い、必要なスキル・将来性を徹底解説
ウェブサイトやアプリケーションの利用が当たり前になった現代において、「フロントエンドエンジニア」という仕事を耳にする機会も増えました。しかし、...
 2
2 -
【2025年最新】プログラミング言語おすすめは? 最新トレンドからなりたい職種と学習方法を決めよう
デジタル化が加速する現代において、プログラミングスキルはあなたの未来を大きく広げる鍵となります。しかし、「どの言語から始めればいい?」「学んだ...
 2
2
239件中1~20件を表示