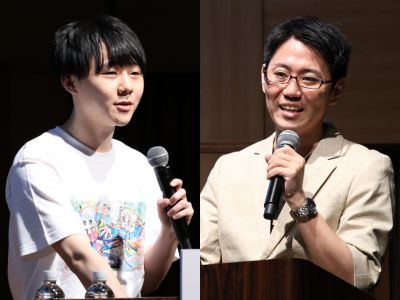「プロダクト開発」記事一覧
-
巨大決済基盤の技術的負債にどう立ち向かうか──DMMが実践した段階的移行戦略
どれだけ事業を支えてきた基盤システムでも、いつかレガシーとして技術的負債の源となる。しかし、新機能開発を優先するあまりに対応が後回しになり、改...
 1
1 -
マネーフォワード流Cursorでの開発自動化方法。「コンテキストエンジニアリング」で一歩先の生産性へ
開発組織の拡大に伴う生産性、品質維持、ナレッジ継承の問題。マネーフォワード関西開発部では、こうした組織の課題に対して、生成AIを使った解決に取...
 9
9 -
30年の実績を持つ「HULFT」をクラウドネイティブ化するまで——ベストプラクティスの探し方
セゾンテクノロジーが30年以上前に発売したファイル連携ミドルウェア「HULFT(ハルフト)」。同社ではこのレガシープロダクトをクラウドネイティ...
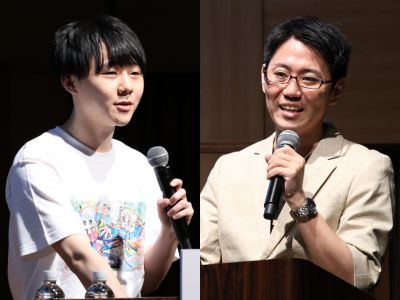 12
12 -
AI面接練習で教育現場の課題を解決! 揺れながら進化し続ける、マイナビ『AI-m』開発の舞台裏
高校3年生の約7割が、面接や書類・小論文によって進路を決める時代。多忙な教員にとって、面接指導の負担はますます大きくなっている。この課題をAI...
 0
0 -
明治は「縦割り組織」をどう乗り越えたか。大企業DXを支えるWellnizeの戦略と実践
「食と健康」のプロフェッショナルとして、いくつもの強力なブランドを有する株式会社明治。そんな明治のマーケティングDX推進を担う株式会社Well...
 1
1 -
データの可視化だけでは不十分——AIも含む「開発プロセス全体」を指標で駆動させる時代へ
データ駆動経営の必要性が叫ばれる中、多くの開発組織が直面するのは「何を測れば事業成果につながるのか」という根本的な問題だ。開発指標を可視化して...
 2
2 -
AIにコードを任せる時代、エンジニアの価値はどこにある?Assuredが実践する「事業を創る」プロダクト開発術
「AIの進化は、エンジニアの役割をどう変えるのか?」「コードを書くスキルだけで、この先も価値を提供し続けられるだろうか?」近年、多くのエンジニ...
 0
0 -
AIエージェント時代に問う、SaaSの未来。開発のボトルネックを解消する「作らない技術」の重要性
「日本のソフトウェアエンジニアを憧れの職業へ」を理念に掲げ、2019年に設立したアンチパターン。経験豊富なエンジニアが結集するスタートアップだ...
 2
2 -
ユーザー6500万超「TimeTree」の進化を支える組織論──ニックネーム文化がAI時代のプロダクト開発を加速する
全世界でユーザー数6500万人超を誇るカレンダーシェアアプリ「TimeTree」。その進化を支えるのは、社長も新入社員もニックネームで呼び合う...
 2
2 -
LLMが開発を誤らせることもある──次世代型ハッカソン「GIFTech」優勝エンジニアに聞く、ソフトスキルが拓く生成AIとの共創
生成AIの登場によって、コードを書くことが容易になった現在、「エンジニアが作り手であり続ける」ためには何が必要なのか。コミュニケーション能力や...
 3
3 -
東京都公式アプリの内製開発が始動! 都民1400万人がユーザーとなるプロダクトの現在地とは
2025年2月にリリースされた「東京都公式アプリ(東京アプリ)」。将来的には都民一人一人がスマートフォンを通じて東京都とつながり、各種手続きの...
 5
5 -
スタートアップでQAチームをゼロから築いた3年──1人目QAが学んだ「個→チーム→組織」成長の法則
品質保証を“文化”として根づかせるには、何が必要なのか。本セッションに登壇したのは、旅行アプリ「NEWT(ニュート)」を運営する令和トラベルで...
 3
3 -
なぜあなたのWebサイトは遅いのか? mizchi氏が語るパフォーマンス改善のポイントとは
Webサイトの“速さ”は、ユーザー体験を左右する重要な指標だ。とはいえ、ブラウザの中で実際にどんな処理が走っていて、どこにボトルネックがあるの...
 47
47 -
「うまい棒1本分」のコストで1年3か月分の処理を高速化! OpenAI Embedding APIで実現するレコメンド機能開発
OpenAI社のEmbeddings APIは、文章をベクトル化し、分散表現技術を活用することで、コストを抑えつつ高度なレコメンド機能を実現で...
 8
8 -
なぜ今「プロダクトエンジニア」が求められるのか? 技術・UX・ビジネスの3領域を越境してユーザーに届ける価値
「プロダクトの価値は、領域の狭間で失われる」。そう語るのは、アセンド株式会社 CTO の丹羽健氏だ。本セッションでは、ユーザーの課題に真正面か...
 3
3 -
プロダクトの価値を高めるためにコーディング以外にできることは?コミュニケーション4つの工夫
「言っていることが伝わらない」「忙しそうで話しかけづらい」――そんな“すれ違い”が、チーム開発の足を引っ張ってはいないだろうか。本セッションで...
 2
2 -
『ホットペッパービューティー』の6年分の技術的負債、返済までの6ステップに見る実践のポイント
「技術的負債」とは、ソフトウェアを長期的に運用することによって、メンテナンスの難易度が上がり、パフォーマンスが低下、コストが増大するなどの問題...
 12
12 -
ユーザー体験を変えたZoom SDK導入の軌跡——mentoが実現したオンラインコーチングの進化
オンラインコーチングの顧客体験を向上させるべく、2023年にZoom SDKを導入したコーチングサービス「mento」。mentoのCTOであ...
 0
0 -
Chatworkからkubellへ、0→1からのBPaaSプロダクト/開発組織立ち上げへの挑戦
2024年7月、Chatwork株式会社は社名を株式会社kubell(読み:クベル)に変更した。中小企業向けビジネスチャットとしてはトップシェ...
 0
0 -
生成AIはプロダクト開発の全工程で使える! それぞれの活用ポイントと効果を最大化する方法をSun Asteriskが解説
昨今、AIの活用は開発現場において不可欠と言っていい。コーディングや業務効率化など、その活用範囲は広がっている。では、事業開発や開発プロセス全...
 1
1
195件中1~20件を表示